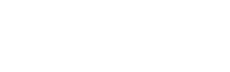ヨドバシのECサイトを技術面で支援するユニバーサルナレッジが解説! ECサイトの売り上げを伸ばす2つの“改善”とは

ECサイトの売り上げを伸ばすにはどうすればよいのか──。この根源的な問いに対する解決策はシンプルだ。それは「サイト内の改善」と「流入の改善」の2つである。これらの改善のためにはコンバージョン率(CVR)やサイトの商品数を踏まえた施策が求められるほか、広告出稿やコストの管理も必要だ。数値を常に確認しながら施策の効果を分析し、次の一手を打って着実に成果を出すにはどうしたらいいのだろうか。
「ネットショップ担当者フォーラム 2022 春」に登壇したユニバーサルナレッジの井上俊一氏は、ECサイトの売り上げを伸ばすためにとるべき施策、改善にあたって押さえておきたい指標などについてわかりやすく紹介した。

「サイト内の改善」を行ってから「流入の改善」を実施するのが鉄則
ECサイトを運営する上で、以下のような課題が発生することはないだろうか。
- ECサイトの売上アップに悩んでいる
- どのソリューションを使えばいいか分からない
- 売上アップを考える上でよい指標はないか
ここでは、こうした課題に対して解決に導く指標を紹介していく。先に結論を述べると、ECサイトの売り上げをアップさせる上で重要になるのは、「サイト内の改善」を行ってから、次に「流入の改善」を行うことだ。この順番がECサイトの課題改善の鉄則となる。
売上アップの施策といえば、セール、検索連動型広告、SEO、ダイレクトメール、レコメンド、特集、SNS、ポイント還元などさまざまあるが、井上氏によると、これらもすべて「サイト内の改善」と「流入の改善」の2つに分類できるという。
サイト内の改善に欠かせない「コンバージョン率」(CVR)
サイト内の改善を図る指標として代表的なものは「コンバージョン率」だ。CVRとは、ECサイトに訪問したユーザーのうち、商品を買ってくれた人の割合を指す。ECの場合は来店人数の代わりに「ブラウザ数」を使ってCVRを算出する式は以下のようになる。
▼買ってくれたブラウザ数÷来てくれたブラウザ数×100(%)=CVR
CVRは次の3要素によって大きく変化する。
- 商品ジャンル
- 商品価格
- 商品数
要素① 商品ジャンル
下記は一例だが、日用品は6.6%、食品は5.4%、専門機器は3.1%、アパレルは3%や1.9%、BtoBだと27.2%というように、扱う商品ジャンルによってCVRは大きく変わる。
要素② 商品価格
CVRは商品価格にも大きく左右される。傾向として、価格が高いとCVRは低くなり、価格が安くなるとCVRは高くなる。
要素③ 商品数
商品数が多いとCVRは低くなり、商品数が少ないとCVRが高くなる傾向がある。「もっとも、これは会社によって変わってくるため一概に言えない」と井上氏は念を押す。
商品数別にみたサイト内の改善方法
ここからは具体的なサイト内の改善方法の解説に移る。井上氏はまず、「商品数によって施策の優先度が変わる」と述べ、商品数別で見たサイトの改善方法について紹介した。
改善方法その① 商品数が少ないサイトの場合
最初は、サイトに商品数が少ない場合の改善方法だ。
極端な例として、1つのECサイトに1商品しかなければ、レコメンドや検索機能などは必要なく、その1つの商品ページがCVRを大きく左右するわけです。そのため注力すべきは「商品ページの改善」となります(井上氏)
その場合のページ改善の取り組みとしては、以下のようなものがあげられる。
- 価格を下げる(セール、クーポン)
- レビューを載せる
- 説明文をわかりやすくする
- 写真をわかりやすくする
- 動画を載せる
- 有名人のコメントを載せる
これらの施策を実施し、結果としてその商品ページのCVRを上げていくことになる。
改善方法その② 商品数が多いサイトの場合
逆に商品数が多くなってくると、商品ページそのものだけでなく、「ユーザーが自分の欲しい商品にたどりつけるか」という要素が大きく影響する。そこで、下記のような施策によって商品への導線を作ることが重要になる。
- カテゴリー:商品を分類したカテゴリーをしっかり整理する
- キーワード検索:キーワード検索が機能しているか確認し、改善する
- 特集(トップページ含む):おすすめの商品を提案する特集コンテンツを充実させる
- レコメンド:別の商品への導線を作るレコメンドを改善する
- ダイレクトメール:お客様に商品を直接案内するダイレクトメールを打つ
これらの施策は、機械的に実施するものと、人力で実施するものの、大きく2種類にわけられる。カテゴリー検索、キーワード検索、レコメンド、ダイレクトメールなどは機械的にやるものにあたり、カテゴリーの分類や特集・トップページのコンテンツ制作などは人力で行わなければならない。
商品数が少ない場合は、上述のとおり商品ページの改善が最優先となるため、説明文・写真の変更やコメント掲載など人力の施策の割合が多くなるが、商品数が多くなるにつれて、検索やレコメンドなど機械的な施策の割合が多くなるというわけだ。
PVが多いページから改善を進めるのがおすすめ
さて、商品数の多寡から打つべき施策がある程度決まったら、次はどこから手をつけていくべきか、改善施策の優先順位を考えたい。井上氏は「ページごとのページビュー(PV)を見て、多いページから改善を行うのがよい」と言う。
たとえば、特集のPVが多いのであれば、コンテンツの内容や掲載する頻度、デザインの見直し、さらにはトップページのデザインの再検討などを行う。あるいは、キーワード検索のPVが多いのならば、検索窓を使いやすくしたり、検索エンジンを入れ替えたりなどキーワード検索から改善していくといった具合だ。
コンバージョン比で改善結果を確認
こうしてサイトの改善を行ったら、次は実際にその改善が効果があったか測定するフェーズとなる。実際に、あるサイトで検索エンジンを変更した例を見てみよう。
検索エンジンを変更した際の効果測定はA/Bテストによって行うのが理想だが、運用の負荷が高くなるため、ここでは、検索エンジン変更前後の「サイト全体」「検索経由」のCVRをそれぞれ見ることにした。
まずは、購入された商品詳細ページの直前が検索ページだった場合は検索経由で商品が購入されたとみなして、下記の通り、「検索経由CVR」を出す。
▼検索経由で商品を買ったブラウザ÷検索を行ったブラウザ数×100(%)=検索経由CVR
このサイトでは、検索エンジン変更前の28日間での全体のCVRが2.27%に対して、変更後の28日間では全体のCVRが1.84%となり、検索エンジンの変更前後でCVRは減少してしまった。検索経由CVRも、検索エンジンの変更前後で2.12%と2.11%となり、ほぼ横ばいだった。
これだけ見ると、改善は失敗しているように見える。しかし、全体のCVRは季節要因などで変動するため、CVRだけで比較するのはおすすめできない。
そこで役に立つのが、「検索経由CVR÷全体のCVR」によって導き出す「コンバージョン比」だという。当サイトのコンバージョン比は、変更前の0.93に対して、変更後は1.15となった。つまり、検索経由のコンバージョン比は上昇しており、検索エンジンの改善施策は一定の効果があったことが読み取れる。
このように、全体のCVRは季節要因などで変動するため、改善の結果を見る指標としてはコンバージョン比を用いるといいだろう。他の施策でも同様で、レコメンドに注力する場合は、レコメンド経由CVRを、特集に注力する場合は、特集経由CVRを算出し、そこからコンバージョン比を導き出すとよい。
「流入の改善」はキーワード広告の出稿を増やすこと
ここまでサイト内の改善について説明してきた井上氏は、次に行うべき「流入の改善」について説明した。
すでに述べているとおり、ECサイトを改善する際は、最初にサイト内の改善を行ってから、次に流入の改善を図るのが鉄則です。この順番が逆になると、投資効果が出ず、お金をドブに捨てるようなものと言っても過言ではありません。(井上氏)
井上氏が言う流入の改善施策とは、ずばりキーワード広告を増やすこと、つまりGoogleへの出稿だ。その際に重要になるのが、“売れている商品”の流入を増やすことである。そのためにまず、サイト内検索のログから検索キーワードと商品のペアを作り、商品が売れている順に広告出稿することがおすすめだ。
ただし、やみくもに出稿するだけではコストが跳ね上がるばかりだ。同時に「コスト率」(売り上げに対する広告費用の比率)はしっかりと確認し、コスト率が一定以下になるようにしよう。なお、コスト率は、以下のように広告費を売り上げで割ることで算出する。
▼広告費÷売り上げ×100(%)=コスト率
たとえばコスト率を2%以下に設定した場合、サイト全体の売り上げが月に1000万円であれば、その2%は20万円となる。つまり、まずは20万円までの範囲で、売れている順にすべてキーワード広告を出稿する。次に、設定したコスト率より高くなりそうな下位のキーワードの出稿を取りやめていくと、パフォーマンスのいい広告が残って、売り上げを伸ばしやすくなるというわけだ。
流入改善にはキーワード広告の出稿は欠かせません。売り上げのコントロールを広告で行うのが理想です。ちなみに、世界最大のECサイトであるAmazonは、大量の広告を出稿して売り上げをうまくコントロールしています。売り上げを広告でコントロールすることが可能な証拠だと言えるでしょう。ぜひ試してみてください。(井上氏)
また、キーワード広告を出稿したら「新規ユーザー率」も常に確認しよう。新規ユーザー率とは、すべての来店者数に対する新しい来店者数の割合を指す。広告出稿によって新規ユーザーがどのくらい獲得できているのかを確認し、キーワードを調整しよう。
まとめ:2つの改善で売り上げはアップする
ここまでECサイトの課題改善について見てきた。まとめると、売り上げアップに向けてはさまざまな施策が考えられるが、それらは、①サイト内の改善、②流入の改善という2つに分類できる。そして、サイト改善は必ずこの順番に沿って改善することが鉄則となる。
① サイト内の改善のポイント
商品数が少ない場合は商品ページそのものの改善、商品数が多いサイトでは欲しい商品にたどり着くまでの導線の改善をメインに行う。まずはPVが多いページから手をつけるとよい。改善後はコンバージョン比によって改善の効果を確認しよう。
② 流入の改善のポイント
流入を改善する手段は、キーワード広告への出稿だ。サイトへの流入ログから検索キーワードと商品のペアを作り、売れている順に出稿していく。その際、コスト率が一定以下になるように調整しよう。売り上げのコントロールを広告で行うのが理想となる。
ECサイトのCVRを向上させるサイト内検索エンジン
ユニバーサルナレッジが提供している「UniSearch(ユニサーチ)」は、AIを活用したECサイト内検索エンジンだ。
ユニサーチを活用すれば、AIによる自動学習最適化でサイト内検索のマッチ率を向上させ、CVRの向上につなげられるほか、今回紹介した改善のための指標もツール内で手軽に確認できる。また、検索キーワードや商品の売り上げなどをユニサーチで確認し、そのままキーワード広告を出稿することも可能だ。井上氏は、「ヨドバシカメラのECサイトを検索技術の側面からサポートしている同社の技術を詰め込んで生まれたサービスです」とアピールし、セッションを終えた。