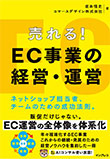ここから、接客の話に入ります。現在のECは、スマホ経由での購入が中心です。移動中などスキマ時間で購入するシーンも多いため、お客さんの購入判断はどんどん短時間になっています。こういった状況に合わせた「端的な商品ページ」の作り方を紹介します。
スマホ前提の商品ページは「要約」が命
現代の商品ページは、スマホ環境で、電車の中やテレビを見ながらなど、集中力の続かない状況で閲覧されることが多いです。また、その構造は「正方形のサムネイル画像を組み合わせたもの」が中心です。いわば10コマ漫画のようなイメージです。1画像1メッセージで、お客さんはフリック操作で商品の概要を把握するという構造になっています。
あなたが販売する商品にはたくさんの情報があり、伝えたいことも色々あると思いますが、このような「お客さんはせっかち」という状況を鑑みると「お客さんが特に知りたいであろうこと」を先に伝えることが大切です。そのためには、お客さんのニーズを理解し「要約して端的に伝える力」が重要。
自分が言いたいことを言う前に、まず「相手が聞きたいこと」や「相手が知るべきこと」から教えてあげましょう。これをアンサーファーストの原則と言います。
アンサーファーストを実践するには、相手が聞きたいことを理解する=顧客理解が重要です。「ダレナゼ」の話、覚えていますか? お客さんは、何の用途・目的で、どういう比較基準で商品を探しているかそれぞれ違います。検索結果の中から「自分の都合にちょうどいい商品」を選ぶというのがお客さんの動き方です。
例えば子供の弁当のおかずの冷凍食品を探しているなら、自分の子供が好きそうか、体に良いかといった観点で比較するはずです。「子供は好きそうかな? OK!」「体に良さそうかな? OK!」というように、心配な点をチェックしながら商品を見ています。つまり、商品ページとは、お客さんの「心の中のクエスチョン」に対する「アンサー」なのです。
制作する前に、「まずリサーチ」が大事
ダレナゼを理解し、アピールポイントを決めるにはどうすればいいか?
一番分かりやすいのは、商品レビューです。どういうお客さんがどういう理由で買ってくれているのかを、レビューを読み込んで理解していきましょう。
- 何が目的で、どういう用途で、どんな経緯で探していたのか
- 似たような商品がある中で、何が決め手になって選んだのか
例えば「子供の卒園式のために色々着回せるレディースフォーマルを探していました。出産してからちょっと体型が変わったので体型カバー機能を重視して選びました」といった声がレビュー内に複数あれば、この商品の「お客さんの興味と決め手」は「体型カバー機能」ですから、それを商品ページでアピールすればよいわけです。他にも「卒園式や入学式など色々使い回せます」などと書き添えるとよさそうです。
もちろん、同じ商品でも人によって感想は違います。同じ冷凍ピザでも、働く親が買えば「子供が喜ぶし、調理が簡単だから」、単身者が買うと「遅く帰ってきてもすぐ食べられて、保存が利くから」などという声が見られるかもしれません。主要な購入理由は一通りページに載せたいので、よく観察しましょう。まだレビューが付いていないなら、類似商品や他社商品のレビューを参考にしましょう。
リサーチの結果、意外なことが分かる場合があります。例えば、エコバッグを販売していて、社内では「素材感」を重視してきたけれど、実際のレビューでは「畳んだ時のコンパクトさ」が評価されていたりします。その場合、当然アピール内容は修正します。
社内取材も重要です。MD担当やバイヤー、社内の職人、販売スタッフ、CS担当に「この商品は何がウリ?」「どんな問い合わせがある?」などと話を聞きます。商品を対面販売しているつもりで口に出してしゃべってもらって録音して、AIなどで文字起こしたものをベースに文章化すると、短時間で情報を整理できます(より詳しい「顧客研究」については法則53を参照してください)。
リサーチが済んだら、商品ページを作る
優先順位を付ける
レビュー分析と社内取材で得られた情報を参考に、アピールポイントを整理し、アンサーファーストの原則に基づいて、優先順位を付けていきます。
具体的には、その商品の「魅力ベスト3」を考えます。自分が伝えたい魅力ではなく、あくまでお客さんから評判の良い魅力で選びます。シンプルな箇条書きで整理してみましょう。例えば前出のエコバッグならば以下のようになります。
- コンパクトに畳めて、ポケットに入る
- 耐荷重10kgで、重い買い物も安心
- 撥水加工で濡れても平気
優先順位が決まったら、テキストや画像で何を伝えるべきか、どんな写真を撮影するべきかのイメージも湧いてきますよね。
画像は「パターン化」すると早く作れる
商品画像は、1枚目には全体の要約、次の画像では「コンパクトに畳める」、次の画像で「耐荷重」、次の画像で「撥水加工」、という流れを作ります。
※AmazonなどECモールによっては1枚目の画像に文字入れ制限があります。その場合は2枚目以降にアピールを書きましょう。
できれば、商品写真の構図や、商品画像のレイアウトパターンは、商品の傾向や購買層ごとなどに、ある程度決めておくのがお勧めです。典型的な構図があらかじめ決まっていれば、撮影時間が短縮されますし、画像制作もスムーズです。詳細は、この後の「ワンポイント」を参照してください。
また、アピールする際は、商品画像とテキストで役割分担することも効果的です。例えばエコバッグなら、画像では「折りたたんだ状態とバッグにモノをたくさん入れた状態」を見せ、テキストで「○kg入れても破れません」などと説明するといった具合です。メリハリを付け、情報を詰め込みすぎないよう注意してください。
テキストは数値やファクトを入れて具体的に
テキストは具体的に書きましょう。
- 数字を使って具体的に示す 例:「軽い」→「重さわずか50g」
- 比喩を用いてイメージしやすくする 例:「大容量」→「500mlのペットボトルが6本入る」
- お客さんの使用シーンを想起させる 例:「撥水加工」→「急な雨でも中身を守る」
そして、一番大切なのは商品名と第一画像(一番上に表示される画像)です。ダレナゼを踏まえて、検索結果で目立つようにするには、商品名の冒頭やサムネイル画像に、端的な強みを一言で追加します。「たっぷり1kg」「雑誌◯◯で紹介」「国産」などと、一言入れるだけでクリック率が倍増した事例もあります。
少ない商品数を工夫して売っていくお店と、たくさんの商品を効率的に登録する必要があるお店では、一品一品にかける手間は変わってきます。商品ページを日々登録・更新していく業務については、法則25を参照してください。なるべく型を作って、パターン化していくと早くなりますよ。
この記事は『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』(インプレス刊)の一部を編集し、公開しているものです。
売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。
坂本悟史 /コマースデザイン 著
インプレス 刊
価格 2,400円+税
ECの仕事を「販売・業務・組織・戦略」の 4分類に整理。現代のEC販売はもちろんのこと、仕入れ・製造から受注・出荷までのEC業務、AIやリモートを活用したEC組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などのEC戦略までをカバー。経営者の学び直し、担当者の育成、組織の共通言語におすすめです。
- この記事のキーワード