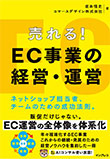かつてはSEOとメルマガだけでぐんぐん売り上げを伸ばせたEC業界。ところが今や、多店舗展開や即日出荷をこなし、SNS運営、動画の制作までしてもなお売り上げが足りない……。「このままで大丈夫だろうか」――そう不安に感じているEC事業者も多いのではないでしょうか。そんな成熟期を迎えたEC市場において、私たちが再び成長軌道に乗るためには何が必要なのか。本連載では、書籍『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則』のエッセンスから、埋もれている“伸びしろ”を発見するヒントをお伝えします。
はじめに:ご挨拶
こんにちは。コマースデザイン代表の坂本です。このたび全21回の連載を担当することになりました。まずは自己紹介を兼ねて軽く経歴をお伝えします。

私は楽天(現:楽天グループ)出身で、マーケティングや出店者さんの支援などを手がけていました。そこからECコンサルティング会社のコマースデザインを立ち上げ、2025年2月に創業から丸17年を迎えました。
コマースデザインでは「経営者や店長さんの顧問」のようなコンサルとして、売上アップだけでなく、業務効率や組織体制、中長期の戦略まで幅広く支援。おかげさまで多くのお店からご依頼をいただいています。
2010年に出版した『売れるネットショップ開業・運営 eコマース担当者・店長が身につけておくべき新・100の法則。』は、おかげさまで累計2.6万部を突破。業界でも多くの人たちに読んでいただきました。2024年には新著『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』を出版し、こちらも好評をいただいています。
近年はセミナーにも力を入れていて、EC事業者向けのAI活用の講演なども行っていますので、機会があればぜひご参加ください。
EC業界は今、成熟期に突入している
さて、本題に入りましょう。私は楽天時代も含めて20年以上EC業界を見てきましたが、ここ数年は成熟期の風を強く感じるようになりました。

上の図は、経済産業省が毎年発表しているECの市場規模や前年対比成長率のデータです。2020年のコロナ禍では21.7%と大きな成長があったものの、2022年からは伸び率が6%未満に落ち込むなど、明らかに勢いが落ち着いてきました。
また、楽天の国内EC流通総額が2024年に初めてマイナス成長を記録したというニュースも、業界の成熟を物語っているように思います(参考:日本ネット経済新聞「【株式公開以来初めて】楽天、国内EC流通がマイナスに 「楽天市場」はプラス成長、三木谷社長「SPU改定なければ4.6%増」」)。モバイル事業の赤字補填のためにポイント還元や販促費の引き下げが影響したと見られますが、それでもマイナスは衝撃的でした。
もちろんEC全体の規模はまだ成長しています。しかし、新興市場として爆発的に伸びていた時代は終わり、世の中の多くの業界と同じように当たり前の成熟した業界になりつつあると言えるのではないでしょうか。
頭を切り替えて、力配分を見直そう
ではこうしたトレンド下において、私たちEC事業者はどうすべきか。私は、まず「頭を切り替えて、力配分を見直すこと」が必要だと考えています。
長年のEC事業運営で、業務手順、販売手法、販路、取扱商品など、リソースやコスト、無駄などが膨れ上がっていませんか? これを見直し、捨てるべきものは捨てる。そうすれば、身軽になって勢いを取り戻すことができるはずです。

そもそもEC事業は、商品を用意し、ページを作ってお客さんを集め、受注・出荷のバックヤードを回しつつ組織体制も整え――と、とにかく付帯業務が多い世界。これが昔は「楽天市場」一本だったのでまだ良かったものの、今では多店舗運営は当たり前、即日出荷もしなければならなくなりました。
現場もリーダーもみんな忙しいので、社内のコミュニケーションは減り、組織体制的にも混乱しやすい状況です。そのまま規模の拡大にひた走れば、当然どこかでほころびが生じるわけです。実際にコンサルの現場でも「業務フローを整備しないまま規模を拡大した結果、属人化が進み、ベテランが辞めた途端に業務が回らなくなった」というケースをいくつも見てきました。これでは規模の拡大どころではありませんよね。
ですから、必要以上に膨れたEC事業のカオス度合いを減らしてシンプルにし、伸びていく成長分野に投資をしていく。自分たちが幸せに商売できる規模を意識しつつ、事業を育てていく。いわゆる「力配分の見直し」が大切なのではないかと私は考えています。
実は伸びしろはまだまだ残されている
「いやいや、やれることをやりつくして伸びしろがなくなったから、規模を広げるしかなかったんだよ」――そんな声が聞こえてきそうです。
ただ、一度立ち止まって考えてみてほしいのですが、「本当にやれることはやりつくした」と自信を持って言えますか? 「あまり考えてこなかった盲点」や「気になりつつも後回しにしたままの仕事」が残っていませんか?
焼き魚は、表面を食べつくしたと思いきや、裏返してみるとまだまだおいしい身が結構残っています。これと同じで、EC事業も表面ではやりつくしたと思いきや、まだまだできることが残されていたりするものです。私はこれを「焼き魚の法則」と呼んでいます。
自分たちにとっての当たり前だけで「やりつくした」「規模を広げるしかない」と判断するのは、もったいないことかもしれません。
私が規模の拡大よりも力配分にフォーカスしている理由は、伸びしろを埋もれさせているお店があまりに多いと感じているからなのです。
マンダラ図で「伸びしろ」をチェックする
ではどうやって“魚の裏側”、つまり盲点になって埋もれている伸びしろを探せばいいのか。そのヒントになるのが、以下に示す「マンダラ図」です。「マンダラ図」は、野球の大谷翔平選手が高校生の時に書いていたというモノと構造はほぼ同じです。

中央に「経営」の円があり、その周囲に4つの色つきの円があります。これは「販売」「業務」「組織」「戦略」の4つが循環することで、中央の「経営」が回っていくことを表しています。具体的には次のようなイメージです。
- まず商品を販売する(青)
- 売り上げが発生すると業務が発生する(オレンジ)
- 業務負荷を分散させるためには組織が必要になる(緑)
- 組織を円滑に回すために戦略や方針が必要になる(ピンク)
- その戦略により販売が増える(青に戻る)
- このサイクルにより、経営が回っていく(中央)
そして経営を囲む4つの円の内側にも、それぞれ小さな円がありますね。これも同じように各円を回すために必要なことを表現しています。
- 販売を回すには、お客さんを集めて(集客)、商品ページで販売し(接客)、リピートしてもらう(追客)プロセスが必要になる
- 業務を回すには仕入れや製造(MD)、販売促進などのストアフロント(SF)に加え、受注・出荷といったバックヤード対応(BY)が必要になる

つまり、ECの仕事はバラバラのように見えて、実はすべてがつながりあう「サイクル構造」になっているということです。
人体にも消化器系、呼吸器系、循環器系などのサイクルがあり、滞ると病気になりますよね。これと同じでEC事業もどこかに穴があいていると、サイクルが滞ってどんどん売り上げや成果が漏れ出て機能不全に陥ります。
なので、あたかも人間ドックをするかのように、この「マンダラ図」に沿ってEC業務全体のやり残しや不足を細かくチェックし、穴(伸びしろ)を特定して埋めていくのです。
伸びしろを埋めると、あらゆることが改善する
「マンダラ図」で見つけた伸びしろを埋めると、あらゆることが改善します。たとえば、組織(緑)における典型的な問題である「リーダーが日々の業務に忙殺され、チーム運営にまで手が回らない」というケース。メンバーとの対話や相談に応じる時間もなく、育成まで手が回らないという状況、覚えのある人も多いのではないでしょうか。
この伸びしろが埋まり、リーダーに余裕が生まれてくると、たとえば以下のように組織(緑)以外にもさまざまな良い影響が連鎖して広がります。
- 新商品を開発する時間が捻出される(オレンジの業務領域)
- 未開拓の集客方法を試すリソースができる(青の販売領域)
- 事業を次のステージに進める方針を検討する(ピンクの戦略領域)
「マンダラ図」に沿って事業を俯瞰(ふかん)し、不調の根本原因や伸びしろを特定して改善していくと、無理なく自然な形で事業を次のステージに進める取っかかりが見えてくるのです。
これが前半でお伝えした、「大規模な拡大」をがむしゃらに求めるのではなく、注力すべき成長分野に絞り込み「自分たちが幸せに商売できる規模での成長」をめざすことの本筋です。
一緒にEC成熟期を乗り越えましょう

長くなりましたが、今回の連載では、拙著『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則』でも紹介する「マンダラ図」をもとに、EC成熟期を乗り越えるためのノウハウをお届けします。
本当は1から100まですべて伝えたいところですが、さすがに全21回では難しいので、基本的には「販売編」の話を中心に紹介していきます。
といっても、SEOやメルマガといった施策に閉じるつもりはありません。これらの販促の土台にある「そもそもどんなお客さん・競合がいて、そのなかで自分たちはどのような理由で選ばれているのか」「自分たちの強みは何で、どういったお客さんにアピールすべきなのか」。こういった本質的な角度から掘り下げていきます。
皆さんの伸びしろ探しの参考になる話ができればと思っています。お付き合いのほど、よろしくお願いします!
次回はEC販売の構造について解説します。自社の商品・サービスがお客さんから「比較されている」こと、きちんと意識していますか?
売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。
坂本悟史 /コマースデザイン 著
インプレス 刊
価格 2,400円+税
ECの仕事を「販売・業務・組織・戦略」の 4分類に整理。現代のEC販売はもちろんのこと、仕入れ・製造から受注・出荷までのEC業務、AIやリモートを活用したEC組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などのEC戦略までをカバー。経営者の学び直し、担当者の育成、組織の共通言語におすすめです。