2025年度も複数の地域でデジタルマーケティング支援事業にて、EC運営やSNS運用の講座に従事していますが、参加者から「自分にはセンスがないから」「センスのある人が羨ましい」といった声を聞くことが度々あります。先日、ある講座で「どうしたら注文が増える良いECサイトになるか」という趣旨を掘り下げてディスカッションしました。今回の「ネッ担まとめ」では、それについて筆者なりの考えをお伝えしたいと思います。
EC運営に必要な「センス」は、知識・観察・情報で培われる
多くの情報に触れて知ることで、理解して判断できるようになる
日本時間10月1日、OpenAIが生成動画に音声を追加できる最新の動画生成モデル「Sora2」を発表しました。その直後から、多くのユーザーが動画をSNS上にアップしています。なかには公序良俗や著作権、肖像権に反するものも多くありますが、本物と区別がつかないクオリティのものも見かけます。
こうした状況はフェイクニュースなど、誤情報拡散にもつながりかねません。けれど、こうした動画のコメント欄を見ると、多くのユーザーが最初は「区別がつかない」「すごい」と驚きながらも、やがて「これはAIか?」と疑うようになり、「これはAIだろう」と見抜く力が養われていっているようすが見受けられます。
これも多くの情報に触れて「知る」ことで、知識量を含蓄し「理解して判断ができる」ようになっていることではないでしょうか。
初心者向け!Sora 2の使い方を解説|導入~動画生成~書き出しまで | note | notta
https://www.notta.ai/blog/sora-2-beginner-guide
使い始めたばかりの頃は、意図しない動画が生成されてしまうことがよくあります。その多くは、プロンプト内の指示が曖昧であったり、互いに矛盾していたりすることが原因です。例えば「大きくて小さい車」のような矛盾した指示はAIを混乱させます。
画角、照明、背景などを細かく指定ができるゆえに、曖昧な指示では低品質な生成結果につながりやすいので、音声文字起こしツールなどを使い、細かく内容を伝えることが重要でしょう。一発で思い通りの映像が作れると思わないことですね。
Googleのガイドラインや、多くのSEO関連メディアでは「ユーザーのために、質の良い価値のあるコンテンツを作り続ける」という主旨が繰り返し伝えられていますが、「ユーザーのためにページ作りをしているのに(順位が上がらない)」と嘆く人に度々会います。
市場はもちろんのこと、購買・行動心理、情報取得ツールによってお客さんが変化していることをインプットしておかないと、「お客さんのためと思っているのは自分たちだけ」になりかねないですよね。
オムニチャネル、OMO――買い物時のストレスフリーな体験提供のために取り組んでいますか?【ネッ担まとめ】 | ネットショップ担当者フォーラム
https://netshop.impress.co.jp/node/14892
10月7日の記事で中林さんが「OMOは当たり前になってきている」と触れていました。そして「実装していない・できていないのに、流行り廃りもありません」とも。
自分が体験しておらず、判断基準も持ち合わせていないのに、良し悪しは決められません。「Instagramで集客したい」という人も多いですが、自分が客側として体験していないのに、「なんだか成功例が多いらしいから、簡単にできるでしょう?」と捉えてしまっていることもしばしばです。
呼吸するように、当たり前に、ECに関する情報を収集してください。私含め3人でお届けしている「ネッ担まとめ」もそんな情報量の一つになれたら幸いです。
要チェック記事
SEO関連
Google検索のフォーラム優遇、Redditの独占と深刻なスパム汚染の実態が明らかに | SEMリサーチ
https://www.sem-r.com/entry/20251005/1759655890
以前から米国では検索結果の上位に「Reddti」や「Quora」といったフォーラムサイトが表示されていました。その他の諸外国では5月頃、日本でも9月頃から、自動翻訳された「Reddit」が検索上位に表示されることが増えてきました。
“結論として、上位100フォーラムの中に新しいサイトや投稿数の少ないサイトは一つも確認できなかった。最も新しいドメインでも2020年または2021年に登録されたものであり、Googleが権威性や歴史を重視していることが示唆される。”
多くの人が介し、知識や経験が共有されるこうしたスペースは、「E-E-A-T」のコンセプトからも、こうした状況になることは無理のないことかもしれません。しかし、この状況にGoogleが何らかの対策を講じることを期待しています。
“今年に入ってからは、LLMO対策と称してnote.com にてスパムコンテンツが増加している。”
先日も、「業務資本提携をしたから、noteがGoogleから優遇されている」という主旨の動画が話題になりましたし、一時期「楽天市場」などのECモールにおいて「検索サジェストで御社名を出す」といった営業もよく聞きました。しかし、こうした根拠がない・規約に反しかねない話に乗っかることは、最悪の場合、サイトがスパム扱いされる、モールからの強制退店などにもつながりかねないので、ご注意ください。「SEOに強い◯◯」にも気をつけたいですね。
AIモードのリンククリックは3%未満!? 見えてきた「AIモードの適切な位置づけ」【SEO情報まとめ】 | Web担当者Forum
https://webtan.impress.co.jp/e/2025/10/17/50237
日本語で「AIモード」が導入されてから1か月半ほどが経過しました。けれど「AIモード」のサジェストには「消し方」「消す方法」「オフ」が並び、「Yahoo!知恵袋」でも「邪魔なので消したい」という投稿が散見されています。長らく慣れていたものが変わる、新しいものが導入される時にはしばしば起こることですが、「AIモード」もすんなり受け入れられているわけではなさそうです。
“AIモードから流入したユーザーは、従来型検索からのユーザーと比較して、セッション時間が短く、閲覧ページ数も少ない傾向にある。”
現時点では、「流入後のパフォーマンスも従来型の検索より低い」というデータもあるようです。今後どのように変わっていくのかも、注視していきたいですね。
SEO施策における課題と不安を探る調査結果 | コマースピック
https://www.commercepick.com/archives/73733
“SEO担当者が抱える悩みは「知識不足」と「社内の理解不足」、そして「リソースの制約」が中心であることが浮き彫りとなりました。”
知識に関しては冒頭の通り、情報収集の量を増やして精査する訓練が大事ですね。社内の理解不足もあるあるですが、これも対話量を増やして、実践・検証できる体制作りをめざすしかないとは思います。
また「SEOを実施する際、課題に感じることは?」に対して、「KPI(指標)の設定が難しい」(53.1%)が最多という結果に。検索順位、流入数、コンバージョンなど、「何をKPIとして選定すべきか難しい」というのは痛いほどわかります。
セッション、PV、コンバージョンだけでなく、エンゲージメント率、滞在時間、閲覧ページ数などさまざまな数値を用いて、社内だけではなく社外の協業先とも「最適な目標は何か?」からすり合わせる取り組みを始めたいですね。
マーケティング関連
フリマ・越境ECが招く“ブランド価値崩壊”。もはや「品質」で選ばれない時代のブランド生存戦略 | MarkeZine
https://markezine.jp/article/detail/49933
“かつてブランドは「ステータスを誇示するもの」であり「品質を保証する安心の印」だった。しかし現在では「自分にちょうど良いものを選ぶための参考基準」としての役割が中心になりつつある。”
10代、20代の人と話していると、多くの人は「自分に合っていれば、コンビニも100均もそれは大事なブランド」で、「無名なモノでも、必要な機能が満たされればそれでいい」と考えているように感じます。それでも、依然として白物家電では有名ブランドが強い支持を集めている傾向も伺えます。
“特にファッションやインテリアといった嗜好品カテゴリでは、「有名ブランド」ではなく「自分にとっての満足感」を優先する傾向が強まっている。”
ブランドの語源を調べてみると、元々は放牧している家畜に「焼印を押す」という行為を意味する古ノルド語の「brandr(ブランドル)」に由来し、所有者を示すための目印だったとあります。「自分のモノはこれ」という語源に近いかたちでブランドは存在しているように思えますから、ECでも「ここがいい」「これがいい」といった役に立つ情報(ヘルプフルコンテンツ)がユーザーに提供されていることが、最適化なのではないでしょうか。
引用記事では、さまざまなアンケート結果が図解されていますので、参考にしてみてください。
福井県のラジコン通販ショップが年商2億円に急成長…社長は業界トップのユーチューバー | 福井新聞
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2423282
“商品レビューやラジコンの基礎知識を紹介するものなど2千本超の動画を投稿。「表情や声の出し方、タイトルの付け方などを勉強した」成果もあり、開設3年で登録者3万人に到達。国内競技人口が1万2千人ほどという業界で、現在は登録者4万4500人、常時視聴数が1万回を超える「インフルエンサー」の地位を確立し、大手メーカー主催も含め国内外のイベントにゲストとして招かれるほどになった。”
冒頭で触れたようなトライアンドエラーの絶対数、訓練を絶やさなかった結果ではないでしょうか。ECの売り上げが8割を超えるとのことですが、人口1.8万人の町で、実店舗などの売り上げも2割ほどついてきていることが驚きです。
地方創生の素晴らしい事例ではないかと感じピックアップしました。
森永の「板チョコアイス」はなぜ消え、なぜ売上倍増で帰ってきたのか? | ITmedia ビジネスオンライン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2510/18/news005.html
“1997年から売り上げが縮小し、2002年春から2003年春にかけて販売を休止していた。”
“その要因の一つが、1998年に実施したパッケージ変更だ。食べやすさを重視して箱からフィルムに変更したところ、「板チョコみたいなアイス」という訴求が弱くなり、他のチョコ系アイスと比べた際の独自性が失われた。”
森永製菓の冷菓事業の主力4商品のなかで最も売り上げを伸ばし、直近5年で2.4倍の成長を遂げている「板チョコアイス」。食べやすさを追求したことで独自性を失い、販売休止に至った話は「お客さんのためにやったつもり」が原因だったのですね。
大手の取り組みではありますが、「販売の通年化」「季節限定商品の展開」「プロモーション戦略」といった施策でV字回復している事例は、ヒントになるところがあるかもしれません。私も大好きな板チョコアイスにそんなストーリーがあったとは驚きました。
今、みなさんにお伝えしたいこと
アオアシに学ぶ「答えを教えない」教え方 自律的に学ぶ個と組織を育む「お題設計アプローチ」とは | 著/仲山進也 小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09311592
ECやSNS講座をしていると、アンケートに「モールの攻略法を知りたかった」「もっとテクニックを教えてほしかった」と書いてあることがあります。また、「EC初心者向けに『月商100万円突破』と題してセミナーを開催したい」というオファーをいただくことも。
しかし、誰もが入手可能な攻略法はすでに出し尽くされているので、テクニックでもなんでもないでしょう。月商100万円も、客単価2000円ほどの雑貨店と10万円の家具店では、まったく施策も異なります。
「こうした」という「回答」はあっても、「こうしなさい」という「正解」は用意するべきものではないと思っています。EC運営でも、この回答の豊富さが大事ではないでしょうか。
楽天大学 学長の仲山進也さんが著者の、人気サッカー漫画「アオアシ」を題材にして執筆した「アオアシに学ぶ「答えを教えない」教え方」という本があります。スタッフ育成や、人材教育に課題を抱える人へのヒントがたくさん書かれている本だと思います。
その著者の仲山さんと、TSUTAYAさん主催で2025年11月6日(木)にイベントを開催します。開催場所は大阪・梅田ですが、もしご都合が合えば遊びにいらしてください。お待ちしております。
「答えを教えない」教え方を紐解く 自律的に学ぶ人と組織はどう生まれるのか? | TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE
https://eventmanager-plus.jp/get/6303455d3c1d172e87592965af9801ebd38160145ea854fc072d968fae3f9dd6#
売れるための「美味しい、普通、美味しくない」「かわいい、おしゃれ、普通、ダサい」といったものにも個人差があります。やはり情報量や知識が、より良く豊富な回答を導くのではないでしょうか。
それではまた次回! 酒匂(さこっち)の「ネッ担ニュースまとめ」をよろしくお願いいたします。
「新・ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」は以下の専門家が連載しています。
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。


















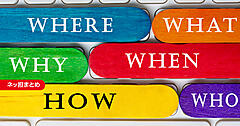














もちろん生まれながらに感覚の優れた人がいるとことは確かです。しかし多くの場合、「センス」は生得的、資格的な特権ではなく、知識・観察・情報蓄積の訓練による判断の総体ではないでしょうか。
講座では、「ECサイトでは、商品だけに限らず、あらゆることを横断して観察することが重要ではないか」という話になりました。家具、食器、衣服、雑貨を見た時、それが北欧系かギャル系か、シニア向けか子供向けかということを多くの人が判断できると思います。
その上で「なぜそう判断したのか」は、インプットされた情報量に基づいているのではないでしょうか。人気の人物、場所、商品がなぜ支持されているのかを知ることで、それらを好きな人の世界観を具体化する知識を貯めていくことにつながり、その良し悪しを自分なりに判断できるようになることが、ECサイトで必要なデザイン、接客などの運営センスとして培われていくのだと思います。
感性だけで片付けず、知識を生かしてデザインや色選定の判断を行うことで「センスがない」という場面を減らすことができるのではないでしょうか。感性に帰着させてしまうことが、育成・教育を困難にするため、豊富な量の知識と、観察・比較で再現可能な判断基準を作ることが重要ですね。
たとえば、今年の流行色が赤だとします。けれど、北欧系の世界観を好む人の赤は一般的な赤とは異なるかもしれない。では「その一般的な赤とは何か」を判断するために必要なことが、知識、情報、経験ではないでしょうか。判断の引き出しを増やし、実際にアウトプットして検証していくことの積み重ねこそが、ECのセンスなのかもしれません。
美味しい料理を食べても、情報が少なければ精度が劣ります。回数を重ねればそれが普通であることになるかもしれない。すごいと思った職人技も、実は当たり前に誰でも行っていることかもしれない。「美味しい、すごい、普通、当たり前」といったことを正確に判断するためには、やはり圧倒的な量をこなさなければいけないですね。