この数年、毎月のように見てきた“SEOオワコン”論争。11月7日に東京で開催された「SearchCentalLive Tokyo 2025」において、Googleは「1998年から毎年のように『SEO IS DEAD』と言われてきている」と話しました。2年ぶりに国内で開催されたこのイベントに参加して感じたこと、関連記事も参考にして、みなさんも本質的なSEOに取り組んでくださいね。
ユーザーの行動は常に変化し、SEOもそれに適応してきた
SearchCentalLive Tokyo 2025のQ&Aセッションまとめ | 海外SEO情報ブログ
https://www.suzukikenichi.com/blog/q-and-a-at-google-search-central-live-tokyo-2025/
Q: 「SEO は死んでいない」と言われるが、ユーザーの行動は明らかに変化している。Google はどのような新しいユーザー行動を観測しており、パブリッシャーは何を意識すべきか?
A: ユーザーの行動は常に変化しており、SEO は常にそれに適応してきた。現在の大きなトレンドは、ユーザー(主に Z 世代が牽引)が情報をより直接的かつ便利に提供されることを望んでいる点である。これが AI Overview のような機能の主な推進力となっている。パブリッシャーは、即時性のある要約された情報へと向かうこの変化を認識すべきである。「Think with Google」のウェブサイトでは、こうした進化するユーザー行動に関する調査やインサイトが提供されている。
Q: AI の台頭により、我々が知る Google 検索は終わったのか?
A: いいえ。
特に終盤にあった「検索は終わるのか?」に対する「NO!」という力強い言葉には、背中を押されるような思いでした。
現在は別物のように扱われているLLMOとSEO。SNSで流れてくるセミナータイトルにも「LLMOはSEOに取って代わるものだから、遅れないように対策を!」と煽るような文言が書かれているケースが多い気がします。しかし2つは新旧や対立するものではなく、「ズボンとパンツ」「ご飯とライス」など同義語のように溶け込んでいくのではないかと考えています。
本質は変わらず、変化と進化に柔軟に対応していくことが大切ですね。以下に紹介する記事もぜひ参考にしてみてください。
要チェック記事
SEO関連
中国のSEOカンファレンスで見えた、AI時代を勝ち抜くためのSEO戦術 | note | SEO研究チャンネル
https://note.com/seolabochannel/n/ne8a3a16241c6
2025年9月18日~21日に中国・深センで開催された「Shenzhen SEO Conference」のレポートです。
"SEOはオワコンじゃない!だが変化は必要だ"
SEOで著名なアレイダ・ソリス氏のセッションでも、「SearchCentalLive」と同様の言及がありました。ユーザーに役立つコンテンツを提供することは変わりませんが、そのユーザーの持つデバイスや情報収集の方法は変化していきますので、それらへ柔軟に最適化していくことが大切ですね。
LLMOとかAIOとかGEOとかじゃなくて、ちゃんとSEOしましょう。【Search Cental Live Tokyo 2025】に参加して | note |
酒匂雄二 / さこっち(Yuh.Sakoh)
https://note.com/sakocchi/n/n60620918f938
"お手伝いするサイトで「これがLLMOです!」とか「LLMOやりましょう!」なんてことは言いません。なぜなら…従来のSEOでAI流入が140倍にもなっているから"
拙稿で恐縮ですが、「SearchCentalLive」に参加して感じたことをつづりました。LLMOという特別なことを意識しているわけではありませんが、AIの普及と共に流入も比例しています。
2025年10月の検索順位変動まとめ【JADE代表 伊東氏の最新SEOレポート】 | マーケトランク
https://www.profuture.co.jp/mk/column/202510-seo-report-jade-ito
本題は検索順位の変動定点観測まとめです。ただ、記事内で妄想として書かれた「怪談:ふたつのキーワードページ」の段落にある、重複・類似ページの統一、リニューアル時に301リダイレクト、404とソフト404を取り違えたり混同したりしたことでサイトに重大な危機を招いている事象に出会うことが、年に何度かあります。
「弘法も筆の誤り」とならないよう、基本は何度も見直すことを心がけたいですね。
AI 検索エンジンの日本国内の「情報源」を徹底比較。「ChatGPT、AI モード、Copilot、Perplexity のトップ 10 引用ドメイン」 | Ahrefs
https://ahrefs.com/blog/ja/brand-radar-top-10-cited-domains/
とはいえ、各種AIがどのようなドメインを回答で引用しているかは知っておきたいところですよね。世界的に有名なSEO分析ツール「Ahrefs(エイチレフス)」によるレポートはとても参考になると思うので、ピックアップしました。
マーケティング関連
推し活マーケティングは購買行動促進に有用も、特有のリスクも 注意すべき2つのこと | ウーマンズラボ
https://womanslabo.com/marketing-research-251111-3
"推しが好きなモノ・コト・人は自分も好き、4割"
推しにまつわる商品やブランドを好きになる人が一定数いる一方、
"推しへの扱い方を誤ると、ファンから「推しやファンを利用している」と受け取られ、逆効果になることがある。ファンにとって推しは非常に大切な存在であり、その推しを応援する行為もまた、尊いもの。だからこそ、企業側の姿勢や表現が少しでも推しやそのファンを軽んじているように見えると、ファンの企業への気持ちは怒りへと変わる。"
私も芸能関係の仕事で、少し苦い経験があります。その際、ある芸能プロダクションの経営者の人から教わった言葉です。
「ファンは、自分たちが利用されている・搾取されていると感じた時、とてつもない拒絶感や嫌悪感に変わることがあります。我々が最も気をつけるべきところなんです」
「良かれと思って」に「独りよがり」が見え隠れすることで、大ケガにつながることを学びました。「お客さんにとってちょうど良い距離感でサービスを提供すること」を意識するきっかけになった体験でした。
クックパッド、7-9月期(3Q)最終は3.5倍増益 | かぶたん
https://kabutan.jp/news/?b=k202511070414
11月7日、国内最大手の料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」を運営するクックパッドの2025年12月期第3四半期が発表され、投資家を中心にSNSで話題になっていました。
有料会員減少による売上減、コスト削減は進んだものの営業利益と従業員数減少がしたことに驚く声もありました。2020年12月期には従業員も550人ほどでしたが、今回の資料では95人と発表されており、人員削減も進めているようです。
2025年12月期 第3四半期決算補足説明資料 | クックパッド
https://pdf.irpocket.com/C2193/lAG8/ELK4/p60P.pdf
現在でも「クックパッド」のレシピは検索結果に数多くリッチリザルトされています。しかしSNSでも「『ChatGPT』に聞いて作った」という料理をしばしば見かけるようになったので、YouTuberや生成AIの登場は影響しているかもしれません。
AIで済むこと・代用できるものは確実に増えているかもしれません。だからこそ、独自性や専門性を磨く重要性は高まってきていると感じます。
映えないSNS「BeReal.」が937%増!「Threads」も222%急伸 2025年SNSランキング発表 | イチオシ
https://ichioshi.smt.docomo.ne.jp/articles/news/58140
Instagramの4230万人、Xの3800人は依然として圧倒的ですが、この2年で最も高い成長率を記録したThreadsはユーザー数が1230万人に、BeReal.はユーザー数がまだ113万人でも、937%増という極めて高い成長率を記録しているとのこと。
「SNSは何を活用すればいいか?」と聞かれることもしばしばありますが、一概に「これ」と言えなくなってきています。いくつか試してみて、継続できそうなもの・相性がよさそうなものに絞り込んでいくのが良いかと思います。
先日、私もXとThreadsに同じ投稿を行ったところ、Xでは約400インプレッション、いいねが3~4だったものが、Threadsではインプレッションが7.4万、いいねは1300ほどつきました。タイミングや反応してくれる人によっても劇的に変わるので、色々試してみることは大事ですね。
今、みなさんにお伝えしたいこと
売上を極大に、経費を極小に (入るを量って、出ずるを制する) | 稲盛和夫オフィシャルサイト
https://www.kyocera.co.jp/inamori/about/thinker/philosophy/words64.html
"経営とは非常にシンプルなもので、その基本はいかにして売上を大きくし、いかにして使う経費を小さくするかということ
(中略)
〔原材料費〕は〔総生産〕の何パーセントでなければならない、とか〔販促費〕はこれくらい必要だろうといった常識や固定概念にとらわれてはなりません。
「入るを量って出ずるを制する」――この言葉の起源は、中国の古典「礼記・王制」に登場する「量入為出(りょうにゅういしゅつ)」ですが、日本ではJAL再建時に稲盛和夫氏が語った言葉として広く知られています。
あるいは「入るを量りて出ずるを為す」とも言われることを親友もよく語っていました。
その親友が長い闘病の末、10月半ばに旅立ちました。余命1年と宣告されてから6年の闘病期間を経てのことでしたので、本当に戦い抜いたと思います。
同級生の彼は教養と知性の塊のような人で、学のない私にいつも学びをくれました。スタートアップや事業承継の支援に注力し、経営学にも長けた人物でした。コロナ禍からの円安、物価高、原料高騰、売り上げを伸ばす要因が多数出てきた2020年代。だからこそ「入るを量りて出ずるを為す」を意識していかなければいけませんね。
親友が旅立ってひと月が経過しましたが、未だ喪失感は計り知れません。「また今度」は来ないかも知れないので、会いたい人に会いに行って話すということを強く考えさせられる出来事でした。みなさんも「またいつか」な約束をしたままでしたら、近いうちに叶えるようにしてくださいね!
それではまた次回! 酒匂(さこっち)の「ネッ担ニュースまとめ」をよろしくお願いいたします。
「新・ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」は以下の専門家が連載しています。
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。



























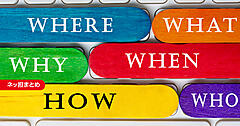






「SearchCentalLive Tokyo 2025」のQ&Aセッションで取り上げられた15個の質問と、その回答の要点をまとめてくださっています。これを読むだけでも、現在とこれからのGoogleの方針に触れることができそうです。
AIOやLLMOといった言葉が混濁する昨今ですが、特にSEOに取り組む人にとって、上記のQ&Aだけでも、本質を変えずにSEOに勤しむことが大切だと再認識できるのではないでしょうか。