「AIを推す」のではなく「AIの推し」になれるように。SEOとLLMOの間とこれから【ネッ担まとめ】
ネットショップ担当者が読んでおくべき2025年3月29日~4月25日のニュース
2025年4月30日 8:00
新年度になり、登壇依頼をいただくことも増えているのですが、そのなかで「LLMO(Large Language Model Optimization)について講演してほしい」「Googleの『AI MODE』が国内で導入された時のことを想定しておきたい」などのお話があり、いよいよAIは不可避であることを痛感している日々です。生成AIによる業務効率化や品質向上を実感している人も増えていると思いますが、私の業務域では「SEOからLLMOに変わるかどうか」の狭間に立っていることをひしひしと感じるようになってきました。「SEOとLLMO」なのか「SEOからLLMO」なのか。いずれにせよ、EC業界でも情報を取得するに越したことはないですね。
AI時代でも信頼とブランド力は大切
SEOは終わらない!AI時代における“信頼”と“ブランド”の力(アレイダ・ソリス氏にブランド強化についてインタビュー) | ミエルカチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=REqCR7weB-U
ブランドは要するに「エンティティ」という意味合いです。企業でも、商品でも、人でもいいのですが、私たちが認識していて、親しみがあって、信頼できて何かしらメリットがあると感じられるものです(00:39)
Googleとしても「これは信頼できる」と判断するための非常に分かりやすい手がかりのひとつとなっているのです(02:33)
最終的に私たちはすでに信頼していたり親しみのあるブランドを選ぶという、ある意味当然の行動を取ってしまいます(03:28)
ブランドというのは、自然な流れの中で育まれていくものだと私は思っています(07:39)
大切なのは、正直に、そして自分の言葉で情報を発信することだと思っています。AIが生成したような中身の伴わない投稿ではなく、自身の経験をそのまま伝えることが最も効果的です(08:12)
かつては「アルファブロガー」という言葉もよく使われていましたが、そういった人たちもブログ黎明期から発信を積み重ねてきたからこそではないかなと思います。
私は「さこっち」というニックネームをSNSでも使い、実際にその名で呼んでもらえることが多いです。現在「さこっち」で検索すると、私のサイトやXのアカウントが上位に表示されると思います。創業当初は他の「さこっち」さんが上位にいましたし、Xには「さこっち」をハンドルネームに使用しているアカウントが200以上あったことを確認しています。
創業当初「SEOをしているのに『さこっち』で出てこないじゃないか」と言われ、悔しさと共に「SEOを主業とする上でそれは良くない」と感じて、積み重ねてきた結果ではないかと感じます。
今では「さこっち」は私の代名詞となり、Googleも「『さこっち』といえば酒匂雄二」となっているのかなと思うと、アレイダさんのお話もごもっともですね。
AI時代でもその知識やスキルの多くがそのまま有効であると実感しているからです(13:40)
SEOからLLMOに変わるのか、並び立つのか、それともどちらかがもう一方に包含されていくのかは現時点ではわかりません。けれど両者は背反するものではなく、これまでのSEOという幹にLLMOという枝葉がついて、それらが一体となって大樹になるのではないか――そんな気がしています。
SEOとLLMOは別物ではなく、真摯にSEOに取り組んでいる人はLLMOにも自然と対応していけるのではないかと考えています。
Googleには通用しないものの、一部で「ChatGPT search」を欺く手法などもリークされていますが、そうした裏技はすぐに淘汰されていくでしょう。それでも、ブラックハット的な手法が次々生まれるイタチごっこは、これまでのSEOと似たような状況になることも想像に難くありません。
だからこそ「SEOに加えLLMOを実践していく」というよりは、ユーザーの課題、悩み、疑問、探し物に対して自社の答えを用意しておく、親切で丁寧なSEOを心がけていけばいいのではないか。現時点ではそう捉えています。
「生成AIが便利、手放せない」と推すのではなく、価値ある独自性の高いサイトをユーザーのために制作し、運営に労力を割くことで、みなさんのサイトがAIの推しになれるよう努めていくべきなのかもしれませんね。
要チェック記事
マーケティング関連
老舗鮮魚店の「売り物にならない魚」詰め合わせ、発売1時間で完売…「見て楽しい」「標本に」 | 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250409-OYT1T50003/
"変わった魚、入荷しました" "Xに投稿、4分で買い手"
餌や廃棄していた魚が2500円の商品に。それ自体が収益源とは言えないまでも、SNSで話題になり言及数が増えて指名検索につながる。そうして本来の主力商品への呼び水となる。店頭の実演販売やワゴンセールのようなことをWebに置き換えてみると面白いですよね。
同姓同名261人、タナカヒロカズついに会社化 何売るの? | 日経MJ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC112ES0R10C25A3000000/
私のクライアントにはアニメキャラと同姓同名の人がいて、スタッフ紹介ページのアクセスが急増したこともありましたが、
"同じようなのが集まってちょこちょこやっている、ミニオンズみたいなものです"
有名製菓メーカー、印刷所、農家、さまざまな同姓同名の人が集まってできた会社の活動、おもしろいですね。これも1つの指名検索によるブランディングなのかも?
同姓同名の有名人とは別に、自分の人物のエンティティをどう認識させる? | Web担当者フォーラム
https://webtan.impress.co.jp/e/2025/04/10/48966
"自分のほかに同姓同名の有名な人物がいる場合も、Googleはそれぞれ別のエンティティとして識別できます"
上記の記事とあわせて。どこで何をしている誰なのかをしっかり発信していくことで、同姓同名でも識別させることは可能ということ。昔、学校で習った「5W1H」がSEOに生きる日がくるとは……。私も「さこっちオブさこっちインジャパン」をめざします。
SEO、検索関連
【コラム】SEOの辻正浩さんにインタビューしたらその使命感に圧倒された | アナリティクスアソシエーション
https://a2i.jp/column/post-38415/
SEO界隈ではその名を知らぬ人はいないであろう、辻正浩氏。
"「検索」という人々の活動は決してなくなりません。SEOは、そうしたプラットフォームやデータベースに適切な情報を反映することです。そう考えれば、検索もSEOも、百年続くと思っています。
一方で、中途半端な今のSEOは無くなっていくでしょう。特に 質を軽視したコンテンツマーケティングはもう無くなります。"
検索もSEOはなくならず、形を変える。そこを見据えたサイト運営を心がけなければいけないですね。
"本当に人々が求めている大切な情報や、不測の事態の速報は、AIでも簡単には置き換わりません。むしろAIが苦手なところだとさえ思っています。"
AIが普及していくからこそ、「AIができないこと」「人だからこそできること」にフォーカスするのも、冒頭のアレイダ・ソリス氏と近しい見解ではないかと思います。
“ゲーミングドメイン”「.esports」、Googleスタッフから「SEO効果はない」とあっさり斬られる。eスポーツチームにうってつけと宣伝してたのに | AUTOMATON
https://automaton-media.com/articles/newsjp/web3-domains-20250421-335883/
「.esports」トップレベルドメイン(TLD)を販売する者がSEO効果を謳い文句にした宣伝を行ったところ、Googleのジョン・ミューラー氏が「そんな効果はない」と断言。現在、元の宣伝投稿は削除されていますが、ジョン・ミューラー氏の指摘は確認することができます(https://bsky.app/profile/johnmu.com/post/3lmtdhn36b22o)。
"このようなTLD ではSEOにプラスの効果はありません"
以前に比べると減りましたが、時々「そのドメインではSEOに不利なので乗り換えを勧める」という営業を受けたという話を聞くことや、商材名やサービスを冠した「shouzainonamae.com」のようなドメインのSEO効果を謳う動画にも出会うことがあります。
読みやすいドメイン、覚えやすいドメインはユーザーにとって親切ですし、ブランディングの観点では大切ですが、SEO効果はないことを改めて認識しておきたいですね。
海外カンファレンス参加レポート 2025年春brightonSEOのセッションとイベントまとめ | アユダンテ
https://ayudante.jp/column/2025-04-21/13-00/#a02
英国・ブライトンで定期開催されている世界最大級のSEOカンファレンスに参加したコガン・ポリーナ氏のレポート記事。非常に有用な情報をまとめてくれています。そのなかの1つとして、
"偽著者プロフィールやフェイクの口コミを用意する文字通りE-E-A-Tの偽装の話だったので、ショックで頭が真っ白になりました(笑)"
「E-E-A-T」も広く知られることになり、「『E-E-A-T』施策」みたいな言葉を見聞きすることも増えました。
「『LinkedIn』がSEOに強い」みたいな話から生成AIでプロフィール画像を作成、権威がある風の人物を仕立て上げ、コンテンツの著者・監修者にしているといった話も聞くことがあるのですが、こうした偽装工作が通じるものではないですよね。
今、みなさんにお伝えしたいこと
ChatGPTに対する「ありがとう」や「お願いします」といった礼儀正しい言葉が数十億円分の電力消費につながっているとOpenAIのサム・アルトマンCEOが発言 | Gigazine
https://gigazine.net/news/20250421-politeness-could-be-costly-ai/
OpenAIのサム・アルトマンCEOがXで発言した内容が話題になっています。口調から冗談のようだとも言われていますが、
"2024年後半に発表されたある調査では、アメリカ人回答者の67%がチャットAIに対して礼儀正しく接していると回答しています。礼儀正しく接していると回答した人のうち、55%が「それが正しいことだから」と回答し、12%は「AIの反乱に備えてアルゴリズムをなだめるために礼儀正しく接している」と回答"
それだけたくさんの「ChatGPT」ユーザーが「ありがとう」と打ち込んでいれば、大量の電力を消費するのは、あながち間違っていないのかもしれません。
そのなかで「AIの反乱に備えて」というのはSF映画のようですが、私の周りでもAIにお礼の言葉を投げかけている人は圧倒的に多いと感じます。かくいう私もその一人。
一方で、AIと会話をすることが増えたからではないかもしれませんが、最近、改めて人と人での礼節の大切さを再認識することも。「こんにちは」「ありがとう」「ごめんね」といったシンプルな言葉をかけるだけで円滑に進むはずのコミュニケーションが、「伝わるだろう」「俺は悪くない」といった思い込みで軋轢(あつれき)を生むシーンに度々遭遇しています。ふと立ち止まり、人に対する敬意などの思いが不足していないか省みたいですね。
AI=あい=愛。私たちの国の言葉の始まり2つで表されるかたち。AIに触れる機会が増すことで、人への愛を失わないようにしていきたいものです。
それではまた次回! 酒匂(さこっち)の「ネッ担ニュースまとめ」をよろしくお願いいたします。
「新・ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」は以下の専門家が連載しています。
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。



























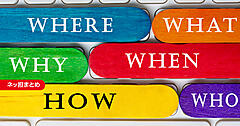





Faber Company 鈴木謙一氏とSEOコンサルタントのアレイダ・ソリス氏の対談。今後のSEOについて、有識者の貴重な見解を聞ける大変有益な動画です。そのなかから、アレイダさんの印象的な発言をピックアップしました。
読み方がわからない未知のブランド、出自が怪しい商品もECモールに出品されるなかで、「知っている」「見たことがある」「友達が使っている」などの情報は確かに安心感につながりますよね。
自社がそうなることは「AI Overview」や生成AIのリサーチで引用される際にもCTRに影響しそうですし、指名検索を獲得できるブランドになることがますます重要になることは想像に難くありません。
角度を変えれば、影響力のあるYouTuberやインフルエンサーとコラボして接触頻度を高めることも一つの手かもしれません。