SEOと広告は"水と油"ではない。「広告を出さないと売れない」「広告を出せば売れる」と考える前にやるべきこと【ネッ担まとめ】
ネットショップ担当者が読んでおくべき2025年3月1日~3月28日のニュース
2025年4月1日 8:00
SEOやECの支援を生業とする前は、私もEC従事者でした。その時、広告費をかけないSEO中心の施策にシフトしたことで、メディアで紹介される際はタイトルなどに「広告費ゼロ」とつくことが多く、「広告否定派」と思われることもあるのですが、決してそうではありません。商材、媒体、ユーザーとの相性、目的が明確になっているかどうか、そもそもない袖は振れませんから、その見極めが大事であるというスタンスです。 「広告をやらないと売れない・広告をやれば売れる」という両極端にならないことも大事です。
「広告を出したら売れる」わけではない。商材、媒体、目的の明確化などが重要
「CMに何十億円投資しても売上も利益も変わらない」かつてキットカットのCMを中止したネスレ日本元社長・高岡浩三氏が考える“テレビCMの価値”「『広告しないと商品が売れない』は時代遅れ」 | マネーポストWEB
https://www.moneypost.jp/1254251
テレビCMは広告メディアのひとつとしてこれからも絶対に生き残ります。ただし、広告をやらないと商品が売れないという考え方は、時代遅れだと思います
自社ECに人を呼ぶために必要な“設計”と“伝え方”──SEOは順位より信頼 | 145MAGAZINE
https://145magazine.jp/retail/2025/03/ec_self-hosted_seo-design/
ただプロフィールを並べるのではなく、「誰に」「何を」「なぜ届けたいのか」という視点を持つ必要がある。ファーストビューにそのメッセージを明確に入れる。ここが曖昧なままでは、訪問者にとって“入口のない家”であり、訪れても何の印象も残らない店舗になってしまう
「ECを作れば売れる」「モールに出店すれば売れる」と勘違いして、大怪我をしないようにすることが大切ですね。
ファン化とは、SEOと接客を繋ぐ“体験の積層”
施策を積み重ねるなかで「自社のサイトを何者なのか確固たるものにする」ことができます。じわじわですが積み重ね。広告は一撃必殺のような効果を出すこともありますが、蛇口をひねりっぱなしでは費用もかさんで経営を圧迫してしまいます。
「お客さまは、なぜあなたの店に来るのか?」「なぜそれを探しているのか?」「どうやって来ているか?」「どんなフレーズで探せたのか?」――これらを積み重ねて準備しておくことが「E-E-A-T」であり、「ヘルプフルコンテンツ」であり、Googleが検索ガイドラインで重んじる「品質」なのではないでしょうか。
どこに何があるのかわからず散らかっていて、店員の姿もなく、尋ねることもできないお店では買い物したくないですし、できないですよね。
要チェック記事
マーケティング関連
消費者が選ぶ強いブランドランキング1位は「YouTube」、2位は「Google」、3位は「ローソン」、4位は「無印良品」、5位は「ユニクロ」 | ネットショップ担当者フォーラム
https://netshop.impress.co.jp/node/13710
知名度や利便性だけではなく、親近性というのも消費者がブランドをイメージし、購買時に選ぶポイントになっているのかも。こうした、商品やサービスを購入する際に最初に思い浮かぶブランドになれるかどうかの「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」は、SEOでいえば「E-E-A-T」の概念と非常に近いのではないでしょうか。
なぜ、ルクア大阪にスタバが「6店」もあるの? それでも売上が好調の秘密 | ITmedia ビジネスオンライン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2503/20/news067.html
地元大阪の話なので食いついたのですが、読むと実に「なるほど」がありました。
"スタバが同じ施設内に複数の店舗を展開できるのは、「ターゲットを変えた戦略」と「ブランドの積み重ね」"
1つのECモールに複数店舗展開している人、自社やモールなど多店舗展開している人、今後予定している人も、スタバに学ぶ点があるのではないでしょうか。
SEO、検索関連
グーグル検索結果CTR調査【最新版】―― 1位CTRは19%~38%と業界格差が拡大【SEO情報まとめ】 | Web担当者Forum
https://webtan.impress.co.jp/e/2025/03/21/48846
検索エンジンの順位ごとのCTRは、目安にはなりますが集計しているデータによって差があるので、注意が必要です。ただ「AI Overview(AIによる概要)」の普及による変化も気になるところなので、分野やクエリの種類による違いは知っておいて損はないかも。
New Research: Google Search Grew 20%+ in 2024; receives ~373X more searches than ChatGPT(新たな調査: Google検索は2024年に20%以上成長し、ChatGPTよりも約373倍多くの検索を獲得) | SparkToro
https://sparktoro.com/blog/new-research-google-search-grew-20-in-2024-receives-373x-more-searches-than-chatgpt/
AIの台によって検索エンジンからサイトへのトラフィックが2026年までに25%減少すると調査会社が予測 | Gigazine
https://gigazine.net/news/20240523-google-ai-search/
1つ目の記事は、世界的SEOツール会社「Moz」創業者であり、SEOの第一人者として名高いランド・フィッシュキン氏が執筆したもの。「Google全体での検索数が1年間で21.64%増加した」と書かれています。
2024年5月に2つ目の記事が出た際も、「Googleはオワコン」「SEOは死んだ」などという意見が散見されましたが、Googleのトータル検索数がむしろ増えているというのは驚きでした。
Google March Core Update Volatility Status(Google3月コアアッデートのボラティリティ状況) | SEARCH ENGINE ROUNDTABLE
https://www.seroundtable.com/google-march-2025-core-update-status-39073.html
日本時間3月14日から展開が始まっている、2025年最初のGoogleコアアップデート。この記事を執筆している3月28日時点で展開は完了していませんが、その初動について。
展開開始直後のSNS上のお祭り騒ぎは、国内でも以前に比べて静かになった印象です。けれど、こればかりは「サイトによるし、ジャンルにもよる」と思うので、交錯する情報は「そういうことも起きているのだな」として、自社や管理しているサイトをしっかり看視することが大事だと感じています。
今、みなさんにお伝えしたいこと
比喩と言語理解 : 言語表現と理解の接点について | 敬愛大学・敬愛短期大学学術リポジトリ
https://keiai.repo.nii.ac.jp/records/2636(参考情報として「敬愛大学・敬愛短期大学学術リポジトリ」のURLを記載しています)
「言語化と比喩」について時々話に出ることがあります。比喩でいえば「作詞家・阿久悠氏は本当にすごいな」と思わされるフレーズがあります。
「男は狼なのよ 気をつけなさい 羊の顔していても 心の中は 狼が牙をむく」
ピンク・レディーの曲「S・O・S」の一節ですが、これで誰にでも言わんとすることが伝わりますよね。童話「赤ずきんちゃん」を読んだことがあれば、幼い子どもですら危ないことはわかる。「あの子の頬は赤いリンゴのようだ」ほど直喩ではないのに。
ですが、「男はシイラなのよ 気をつけなさい」と言っても、ほとんどの人は「え?」となりますよね。シイラが動くものには何でも食いつくさまや、釣り上げると色が変わるさまから「交際すると豹変する」など、シイラが「軽い人の比喩」とはなかなか伝わらないかも。なので、自分だけにわかる比喩・変換は言語化ではないのかもしれません。
喩えは、その場にいるほとんどの人に伝えるには便利ですし、「今日の場の人はこういう傾向だから」と、その場に即した喩えをぱっと出せる人は頭が良い人だろうなと思います。釣り人が集まる飲み会なら、シイラの喩えもウケるかもしれません。
ECサイト育成やWebサイトのアクセス分析などで、私と同年代が多いチームなら「ドラクエでいうと『はがねのつるぎ』を手に入れたくらい」「船が手に入ったあたり」という喩えで状況の共有が捗ることもしばしばあります。
さきほどの頬の話で言えば、「あの子の頬が赤いのは、暖房が効いている部屋にいるにもかかわらず厚着をしているからかもしれない。しかし発熱している可能性もあるので、軽装になるようにすすめるか、念の為体温も計っておいたほうが良いかもしれない」が言語化でしょうか。言語化と比喩(自分向けに納得するものと大勢で共有できるものもある)の違い、おもしろいですね。
それではまた次回! 酒匂(さこっち)の「ネッ担ニュースまとめ」をよろしくお願いいたします。
「新・ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」は以下の専門家が連載しています。
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。




























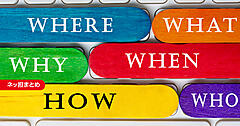






逆に「広告を出したら売れる」でもなく、やはり商材、媒体、ユーザーとの相性、目的を明確にすることが大事ですね。認知拡大、ナーチャリング、ブランディング、売上獲得、何をもって広告を行うのかが重要ではないでしょうか。
冒頭で書いたように「広告ゼロ集客でSEO」を強調されることが多いのですが、当時の私は広告費を捻出しがたい状況だったので、結果的に広告費をゼロにして集客しなければならなかったに過ぎません。そのなかで、自分と相性の良いモノがSEOだったのです。現在では、EC事業者さんと広告代行会社さんと共に三位一体で取り組むことも増えました。
その際は、競合がSEOに注力おらず、広告を出さなくてもSEOで集客を図れそうな商材、SEOの難易度が高く、広告でなければ導線を作れない商材など、自社が置かれている状況を見定め、ECとお客さんが出会える場所を健やかに増やしていくことを協議しながら、予算、出稿先、広告のクリエイティブを行うことを意識しています。
ですので、いかに広告費をかけようとも受け皿であるEC側が整備されていないとコンバージョンには至りにくくなりますから、"ECサイト=実店舗のような設計"が重要です。
ECカートシステム「futureshop」を提供するフューチャーショップ 取締役の安原貴之さんと、ECサイトを家に見立て、その家の設計について対談しました。