ファンがファンを呼ぶECサイト「タマチャンショップ」はなぜ愛され続けるのか。リピート率7割を実現する施策とは
「楽天SOY」8度受賞、「JAPAN EC大賞2024」総合大賞を受賞した宮崎発のECサイト「タマチャンショップ」。リピーター7割&会員数140万人を達成する秘訣を九南サービス代表の田中耕太郎氏に取材した
2025年4月16日 8:00
美容・健康に特化した「食」にまつわるオリジナル商品を販売する、宮崎発のECサイト「タマチャンショップ」。しいたけ農家が自社の「しいたけ」を販売する目的で2003年に立ち上げたECサイトだったが、今では約140万人の会員を持つ人気ブランドに。「楽天市場」で8度の「ショップ・オブ・ザ・イヤー(SOY)」を受賞したほか、一般社団法人日本通販CRM協会が主催する「JAPAN EC大賞2024」では総合大賞を受賞。口コミを中心に支持を集め、リピーター率は約7割にのぼる。なぜ「タマチャンショップ」は愛され続けるのか。九南サービスの代表・田中耕太郎氏に聞いた。
「パーパス」を定義して、「ストーリー」を伝え続けた
「ニッポンのおかあちゃんになりたい」――そんなキャッチコピーを掲げ、美容・健康に特化した食品やドリンク、コスメなど「食」にまつわるオリジナル商品を販売する「タマチャンショップ」。今でこそ約140万人の会員を抱える繁盛店だが、「立ち上げ当初は順風満帆ではなかった」と田中氏は振り返る。

開業の目的は自社栽培の「しいたけ」を販売することで、それ以外に九州で採れた農作物を使った食品も扱っていました。「売り上げを伸ばすぞ」と息巻いて始めましたが、だんだんとつまらなくなってきて……。競合もまったく同じ商品を販売しているので安くなければ売れず、価格競争に疲弊してしまったんです。(田中氏)
他社から商品を仕入れ、競合よりも安く売るビジネスモデルに限界を感じた田中氏は、方向転換を決意。まずは、自社の「パーパス(存在意義)」を定義して、ECサイト内にコンセプトページを立ち上げた。
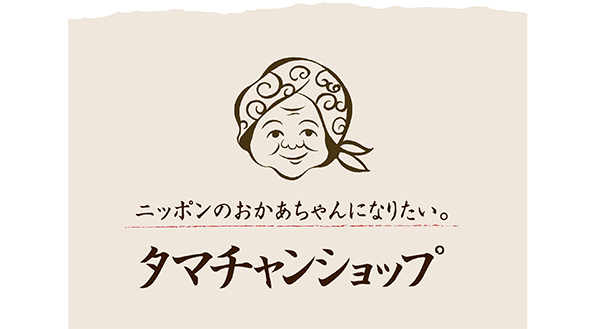
ECサイトは、とにかく「売りたい気持ち」が先行しがちです。そうではなく、おいしい食品を通じて美容と健康に貢献したいという「『タマチャンショップ』を通じて実現したいこと」を丁寧に伝えていきました。コンセプトページをはじめ、商品ページ、商品への同梱チラシ、メールマガジン、SNSなどで自社のメッセージを発信し続けました。(田中氏)
その際に徹底したのが「世界観の統一」だ。デザインやテキストの基準を明確化し、トンマナを統一。顧客の目に触れるものは基準に沿って制作することで、自社のビジョンがブレないように配慮した。そうしたブランディング施策を始めてから4~5年が経過し、ようやく「タマチャンショップ」の文化が形成されてきたという。
同時並行でオリジナル商品の開発にも着手。徐々にオリジナル商品の割合を増やしていき、2010年頃からは完全シフトした。現在は16の自社ブランドを抱えるまでに拡大している。

商品開発の基準は、「友達に薦めたくなるか」
「タマチャンショップ」では、ナッツやドライフルーツ、ドリンクパウダーや健康食品など多彩な商品を扱う。「オリジナル商品を、どう生み出しているのか」とたずねると、田中氏からは意外な回答が返ってきた。
これまでは市場調査などをまったく行わず、「自身の感覚」を最も重要視してきました。自分が心からほしいモノ、既存商品では解決できない課題などが商品開発のきっかけです。「熱量高く友達に薦めたくなるような感覚」を大事にしています。(田中氏)
たとえば、5000万食を突破した人気シリーズ「タンパクオトメ」は、まさにそうした視点から生まれた商品だ。動物性+植物性プロテインと25種以上の美容成分を配合した“美容専門”プロテインで、15種類以上の味のバリエーションを展開。リピートする愛用者も多い。

女性専用のプロテインを大々的に訴求したのは、当社が初めてではないかなと。発売当初は「プロテインを飲むと太ってムキムキな体になる」というイメージがあり、それを払拭するために文化の啓蒙から始めました。ファッションイベント「ガールズアワード」と共同開発して、「健康的なダイエットや美容にはタンパク質が欠かせない」というメッセージを伝えていったところ、4~5年かけて支持が広がりました。(田中氏)
「三十雑穀」シリーズも、「タマチャンショップ」を代表する人気ブランド。以前は「21世紀雑穀米」として21種類の雑穀を使った商品だったが、「1食で30品目を食べられる」をコンセプトにリブランドし、さらなるヒットにつながった。

過去には「ご飯を食べると太る」とお米が敵対視されていた時代があったのですが、「ご飯1杯で30品目が食べられて健康的な食事になる」「ご飯を味方にしよう」と訴求して、人気獲得につながりました。現在は、レンジ調理で食べられる「三十雑穀パックごはん」や雑穀から作った味噌に出汁を加えた「三十雑穀スープ」など幅広く展開しています。(田中氏)
手軽にカルシウムを摂取できる「OH!オサカーナ」は、既存のお菓子をアップデートしてヒットにつなげた商品で、累計販売数は600万袋を超える。昔からある「アーモンド小魚」をヒントに「どうしたらもっと日常的に食べてもらえるか」と思考を凝らし、さまざまな食品やフレーバーと組み合わせた。現在は約20種類を展開する。

「OH!オサカーナ」は、お子さんと一緒に家族で食べられるおやつとして高い支持を得ています。昔からあるお菓子ですが、栄養素が高くておいしいのに注目されていないことに着目し、新しい洋服を着せる感覚でアップデートしました。良い先行事例になったと思います。(田中氏)
ファンの「熱狂」を生み出す「リアル店舗」と「コミュニティ」
ECサイトとして一定の成功を収めた後、「タマチャンショップ」はリアル店舗にも進出。宮崎県都城市の本店、福岡や大阪など7店舗を運営する(2025年4月時点。2店舗が直営、5店舗がフランチャイズ)。リアル店舗を開業したのは、「オンラインの弱みを埋めるため」だという。

オムニチャネル戦略を掲げていて、オンラインのデメリットとなる「体験」や「おもてなし」をリアル店舗で強化しています。自社製品を使ったメニューを提供する飲食店を併設する店舗もあり、当社のビジョンや商品への理解を深めています。お客さまの熱量はオフラインのほうが圧倒的に高く、SNSを通じた口コミも広がりやすい。「ファン作り」においてリアル店舗は欠かせない存在です。(田中氏)
宮崎から始まり関西にも進出しているが、関東には店舗を持たない。「東京は1つのゴールと設定していて、出店の際は全力を尽くしたい。現状は土地探しをしている段階」と田中氏は説明した。
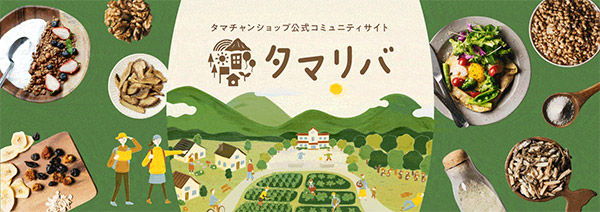
2023年にはファンとのつながりを強化する場として、コミュニティサイト「タマリバ」を開設。「タマチャンショップ」のビジョンに深く共感するファンが集うコミュニティで、約5000名が在籍している(2025年4月現在)。
コミュニティでは、商品を使ったレシピを投稿したり、ファン同士が交流したり、スタッフへの意見や質問を受け付けたりしている。会員と一緒に新商品の開発を行うこともあるという。サイトでは日々多くの投稿がされるなど、活発に利用されている印象だ。
開設から約2年で、投稿数は1万件以上にのぼります。“村”のような雰囲気にしたいと考え、立ち上げの1年間はクローズドで運営してきました。コアなファンの方が集まっていて、お客さま同士が商品を紹介し合う理想的な状況です。(田中氏)
オンラインとオフラインを融合させ、顧客とより近い位置で、頻度高く交流することで、ファンの熱狂を生み出しているのだ。
課題は「時代の変化」にどう対応していくか
美容や健康に高い関心を持つ30~40代の女性を中心に、多くの会員を抱える人気ブランドとなった「タマチャンショップ」。多数の受賞歴を持つが、どのような点が評価されているのか。
受賞の明確な理由はわかりません。数字だけでいうと、2024年は絶好調ではありませんでしたし。おそらく、地道なストーリーの発信やきめ細やかな接客、妥協のない商品開発なども加味して評価をいただいているのだろうと思います。(田中氏)

そんな「タマチャンショップ」のこれからの課題は、「時代の変化にどう対応していくか」だと田中氏。
物価高の影響に伴い、消費者の感情の変化が見られます。「これを買うことで、どんな自分になれるのか」を熟考する「意味消費」のような時代になっていて、納得してもらうためのハードルが非常に上がっています。ファンになっていただくには、1つの型にはめた伝え方ではなく、1対1の接客が求められます。(田中氏)
とはいえ、実際に1対1の接客を全員にするのは不可能だ。そこで、AIなどの技術を駆使して、それぞれの顧客に向けて“パーソナライズ化したメッセージ”を届けることを考えている。そのための人材育成やリソースの確保が課題になるという。

ライフスタイルの多様化に伴い、商品開発にもさらなる工夫が必要になる。現在、「タンパクオトメ」は「飲む」から「食べる」へのアップデートを検討、さらにウェルビーイングにつながるような「夜専用プロテイン」の開発にも取りかかっているそうだ。
日本食が海外でも高く評価されていることを踏まえ、海外展開にも注力する。すでに海外企業との取引が増えているが、海外売上比率は5%未満にとどまる。今後5年以内に国内と国外の売上比率を5:5にすることを目標にしているという。
等身大の思いを伝えながら、顧客の声にも耳を傾け、絶え間なく進化し続ける。それが「タマチャンショップ」が愛され続ける理由なのだろう。
- この記事のキーワード
































