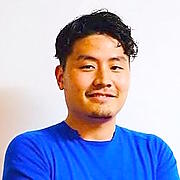「アトツギ」とは、先代から受け継いだ価値を時代に合わせてアップデートする存在です。特に老舗ブランドにおいては、伝統を守りつつ新しい顧客や市場との接点をつくる役割を担います。実は、その実践の場として注目されているのがポップアップストアというのはご存じですか? 短期・小規模で展開し、既存チャネルに負担をかけずに新商品や新価格帯、異なる顧客層に向けたチャレンジできる場として、注目を集めているのです。この記事では、「アトツギ」がポップアップを再成長の装置としてどう活用しているのか考察します。
- アトツギにとってポップアップストアは、既存のブランド資産を損なわずに新しい挑戦を試せる“別レーン”
- 春華堂や本和菓衆の動きに共通するのは、後継者世代が「実演・編集・コラボ」といった即興性を武器にした顧客関係の再構築
- 売上ではなく、継承の手応え・新規の接点・次への材料をどう持ち帰るか──この視点があるかどうかが、ポップアップストアを一過性で終わらせるか、再成長の装置にできるかの分岐点となる
「アトツギ」の視座:受け継いだ資源の功罪
「アトツギ」は、先代から経営資源を引き継ぐ後継者を指します。単に会社や店舗を継ぐだけではなく、受け継いだブランドや技術、人材や取引先といった資産を守りながら、社会や消費者の変化に合わせて新しい価値を加える役割を担うのが特長です。
ただし、「アトツギ」は資産と同時に、消費者が抱く強い先入観や固定的なイメージも引き継ぎます。看板が重いほど、新しい挑戦は慎重にならざるを得ません。
こうした利点と課題を両立させるために有効なのが、常設店舗や既存チャネルとは切り離された「別レーン」です。短期・小規模で検証ができるポップアップストアは、「アトツギ」にとってリスクを抑えながら仮説を試し、数字と顧客の声をもとに意思決定できる実践の場となります。
「アトツギ」にとっての実験と検証の場「ポップアップストア」
ポップアップストアは「短期・小規模で展開できる施策」として広く知られていますが、「アトツギ」にとってはそれ以上の意味を持ちます。
既存の資産を損なわずに、新しい挑戦を試せる実験の場であり、課題を整理できる検証の場になるからです。
ここで検証できるポイントは大きく2つあります。
- 商品や価格の検証:新しい味や素材、容量、価格帯を試し、どの組み合わせが受け入れられるかを見極める
- 新たな顧客層との出会い:既存顧客ではなく、通勤客・観光客・若年層といった新しい層にどう響くかを確かめる
ポップアップストアは「アトツギ」にとって、小さな仮説を低リスクで試し、数字と顧客の声を持ち帰る場として機能するのが最大の特長です。
お薦めのポップアップストア出店スペース
ポップアップストアと一口に言っても、その形態はさまざまです。「アトツギ」が「まず試す」場として相性の良いスペースタイプを3つ紹介します。
- 商業施設内のイベントスペース
施設全体の集客力を生かせるため、新規顧客層との接点づくりに向いています。特に和菓子やスイーツは、百貨店のデパ地下に代表されるように、買い回り動線に自然に組み込まれやすいのが特徴で相性が良いスペースです。 - 駅ナカ・駅チカの催事スペース
通勤客や観光客といった日常的にブランドと接点を持たない層に出会える場所です。短期間でも高い通行量を確保できるため、新商品の反応を試すのに適しています。 - 路面のシェア型スペース
ブランドの世界観を自由に演出できるのが利点です。既存の常設店舗とは異なる雰囲気を打ち出すことで、若い世代やSNS発信と親和性の高い試みができます。
事例から見る「アトツギ」の挑戦
本和菓衆@銀座三越:若旦那たちの共同実験

全国の老舗和菓子店の若旦那衆10人で結成された「本和菓衆」。東京・銀座三越で12回目の開催となった2024年冬に「本和菓衆 12 ~自由な感性と受け継がれる技~」と題し、いま一度和菓子の原点に戻って、もっと自由に、素直に、伝統的な製法や材料、形にとらわれない新作和菓子が期間限定の催事を実施しました。
伝統の技法を守りながら、シュトーレンとの協働や実演販売など、“今ここ”を編集した取り組みを披露。百貨店という場で固定ファンに加え、普段は接点を持ちにくい層と対話が生まれました。世代交代期にある経営者同士が共同で企画し、それぞれの学びを持ち帰る形式は、「アトツギ」ならではのポップアップストア活用といえます。
春華堂「HOW'z」:原宿の新施設でテーマを入れ替える仕掛け
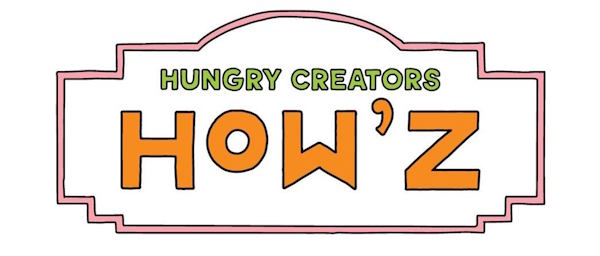
「うなぎパイ」で全国的に知られる春華堂は、山崎貴裕氏(3代目)が代表として経営を担っています。
「うなぎパイ」は観光土産としての知名度は高いものの、商品イメージが固定化しやすく、日常的な利用や若い世代との接点づくりに課題を抱えていました。その解決策として「アトツギ」が立ち上げたのが、原宿の商業施設に構えた「HOW'z」です。
山崎氏は「まちづくり」「地域資源活用」を軸に新たな展開を進めており、常設でありながら期間ごとにテーマや商品を入れ替える方式を取り入れ、ポップアップストア的な柔軟性を確保。若者文化の中心地で親ブランドのイメージを背負いすぎずに挑戦する姿は、「アトツギ」ならではの戦略として注目されます。
5.「アトツギ」がポップアップストアで確認すべき3つの成果
ポップアップストアは期間中の売上だけでは評価できません。世代交代期にある経営者にとって重要なのは、どんな成果を持ち帰れるかです。
- 先代の顧客をどう引き継げたか
長年の固定客が新しい提案をどう受け止めたのか。従来の支持基盤を崩さずに更新できたか - 新しい顧客層に“橋”をかけられたか
若年層や都市部の来訪者など、これまで接点の薄かった層がブランドとつながるきっかけをつくれたか - 資産をどう次につなげられたか
商品開発・販売導線・会員データといった資産を、常設店舗やECに還元できる形で持ち帰れたか。
単なる「売れたかどうか」ではなく、“継承”と“刷新”を同時に進める「アトツギ」特有の視点です。この整理ができると、ポップアップストアは一過性の施策ではなく、ブランドを次の世代へつなぐ学習サイクルとして機能します。
まとめ 小さな実験を積み重ねて再成長へ
「アトツギ」は、受け継いだ資産を守ると同時に、新しい価値を加える責任を担います。そのバランスを取るために、ポップアップストアは有効な選択肢です。短期の挑戦を繰り返し、得られた成果を常設やECに還元する。その積み重ねが、やがて老舗の再成長を支えることにつながっていきます。
- この記事のキーワード