Eコマースにおける生成AI活用は「テキスト化のスキル」「活用で業務をよりラクにできる発想」が求められる
Eコマース業界でも注目度が高く、活用範囲が広がりつつある生成AI。EC事業者がAIを活用するために必要なこと、留意すべき点などを、マーケティングテクノロジストの柳井隆道氏にインタビューした(連載第30回)
2025年7月2日 7:00
Eコマース業界でも注目を集める「生成AI」。商品のキャッチコピー作成から戦略立案まで、その活用範囲は日々広がりを見せている。一方、その本質を理解せず、誤った解釈をしている人も少なくない。今回、東京大学在学中からエンジニアとしての経験を積み、現在マーケティングテクノロジストとして活躍している柳井隆道氏(Option合同会社 代表社員)に、データとテクノロジーの最前線から見た生成AIの現状とネットショップ運営の課題について話を伺った。前半のこの記事では、生成AIを活用してECサイトの売れる商品説明文などを作る際に必要なスキルなどについて話している。
生成AIに関して参考になる情報とは?
竹内:柳井さんは「マーケティングテクノロジスト」として活躍していて、ネットビジネスにおけるデータの計測から、整理、活用提案などを企業に対して行っています。東京大学在学中に統計学を学んだことがデータ解析に興味を持ったきっかけと伺っていますが、そこで学んだ知識も、生成AIへの興味につながっているのでしょうか。
柳井氏:興味としてはつながっていますが、知識としてはあまりそのまま使えることはありません。統計学はスモールデータを前提とした古い学問で、実験や調査結果を理論付けるためのツールです。一方、生成AIの機械学習やディープラーニングは、ビッグデータを扱うコンピューターサイエンスの流れからきていて、統計学とは系譜が異なります。
竹内:ビッグデータとスモールデータでは、根本的な考え方が違うんですね。私のようなテクノロジー分野が苦手な人間だと、その違いすらわかりません。特に生成AIに関しては専門書だと内容が難しすぎて理解できず、かといって平易なビジネス書では情報のエビデンスが怪しくて、何を参考に情報収集をすればいいのかわからないところがあります。
柳井氏:生成AIの最先端研究を行っている東京大学の松尾・岩澤研究室から発信されている情報は信頼できると思います。彼らは大学内だけでなく、外部にもカリキュラムを提供していて、書籍も多数出版しています。正しい生成AIについて学ぶのであれば、この研究室の教材が参考になると思います。

生成AI利用時は「目的を明確にすること」が重要
竹内:2023年に「ChatGPT」が登場しましたが、柳井さんも「おおっ!」と驚いた側なのでしょうか? それとも、その前から生成AIの技術の存在はご存知だったのでしょうか?
柳井氏:生成AIの技術自体は知っていました。元々AIは機械学習の技術で、大きく「予測」と「生成」の2つに分類されます。「ChatGPT」はそのなかでも「生成」の技術ですよね。私は予測の方を専門としていたので、生成という技術も知識としては知っていましたが、「こういう形になったんだな」というのが率直な感想です。
竹内:では「ChatGPT」が登場した時、「これはビジネスで使える」と思ったんですね。
柳井氏:いや、最初は疑いがあって。そして、使っていくうちに「やっぱり疑った通りだったな」と(笑)。生成AIはビジネスツールとして活用すべき部分が大いにあるし、どんどん試して使うべきだと思っていますが、「生成AIが言っているから正しい」と盲信し過ぎることは、あまり良くない傾向だと思っています。
竹内:どういうことでしょうか?
柳井氏:生成AIを使用する際に意識すべきことは、「何のために生成AIを使うのか」利用目的を明確にすることだと思っています。知識を求めるのか、作業を効率化したいのか、それともクリエイティブなコンテンツを生成してほしいのか――使い方と目的によって、導き出される回答の精度は大きく変わってきます。
特にマニアックな分野や専門的な分野、細かい言葉尻、たとえば一文字違うだけで意味がまったく異なるようなものは、不正確な回答を出してしまうケースが多いです。技術用語なども「これはまったく違うぞ」ということがよくあります。
「何が売れるのか」などプロンプトに十分なコンテキストを与える
竹内:コンサルタントの現場でも、ニッチなマーケットを調べようとしたら抽象的な回答しか出てこないケースが多いです。限られたマーケットの、さらにEコマースに絞り込んだなかで、ネットショップの売れるキャッチコピーを生成AIに考えてほしいとなると、かなり専門的な分野の回答を求めることになりそうですね。
柳井氏:もし、ネットショップの売れるキャッチコピーを生成AIに考えてほしいのであれば、まずは何が「売れる」のかということを、プロンプトにコンテキスト(文脈)として与えなくてはいけません。生成AIは、ある事象が起こるという条件のもとで、別のある事象が起こる「条件付き確率」で回答しているので、「最もありそうなもの」「無難なもの」を返すロジックになっています。
つまり、今与えられている状況や材料のなかで、最も多数派の回答を返すだけなので、その条件がぼんやりしてしまうと、どうしてもぱっとしない回答を返してしまうところがあります。
竹内:条件をもっと細かく設定して、具体的なプロンプトを入力しなければ、ネットショップで売れるキャッチコピーや商品説明文を生成AIに書かせることは難しいということなんですね。
柳井氏:生成AI運用のコツは、プロンプトに十分なコンテキストを与えることなんです。たとえば「何が売れるのか」という判断基準や、「ターゲットは誰か」「どんな状況で使うものか」「何を解決する商品なのか」「使うことでどんな風になれるのか」などの条件を適確に与える必要があります。そうすることで、生成AIはより質の高い回答を導き出すようになり、顧客の消費心をくすぐる言葉を生み出してくれるようになります。

(画像は「アナリティクス アソシエーション」のサイトからキャプチャ)
生成AI利用で必要なことは「テキスト化のスキル」
竹内:でも、そんな精度の高いプロンプトを書き出せる人は少ない気がしますが……。
柳井氏:その通りです。だからこそ、これからの時代に求められるのは、自分の欲しい回答を生成AIに導き出させるための「テキスト化するスキル」ではないかと思っています。
竹内:文章を書くことが苦手な人にとって便利な生成AIが、実は文章を書くスキルが最も求められるツールになるんですね。これは想定外の見解です。でも、売れるキャッチコピーに限らず、売れる商品や売り方などは、常識を超えるような斬新な発想から生まれるケースが多いです。こうした突飛な発想も、プロンプト次第で生成AIに作らせることは可能なのでしょうか。
柳井氏:想像を超えるものや突き抜けた考え方を生成AIに導き出させることは難しいと思います。「80点のものは作れるけど、120点は無理」というのが今の生成AIではないでしょうか。ある程度のクリエイティブな仕事はやってくれますが、今までの枠組みをすべて外れたようなことは生成AIが苦手としているので、そういう作業は今後も人間の仕事になってくると思います。
売れる言葉は「執着心」で作る
竹内:生成AIの作る文章を「読みにくい」と感じる人もいれば、「読みやすい」と感じる人もいます。個人的には、文章力のない人ほど「生成AIの文章は読みやすい」と言っているような気がしていて、まだまだネットショップのような「人にモノを買わせる」というレベルの文章には達していないように感じています。
柳井氏:そのあたりも、「〇〇に向けた文章だから、もっと噛み砕いて書いて」とか「フォーマルに書き直して」といったプロンプトで文章の読みやすさは調整可能だと思います。今の生成AIの文章のクオリティであれば、顧客満足度の高い文章のレベルにまで達しているのではないでしょうか。
竹内:なるほど。私自身、ネットショップを運営していた経験があるせいか、売れる文章に対する判断基準が他の人より厳しめなのかもしれません。クリエイティブな仕事に慣れている人は、どこかでキャッチコピーや文章のクオリティの妥協点を見つけていかなければ、生成AIを使いこなして仕事を効率化していくことが難しそうですね。
柳井氏:作業にどこまでこだわって、どこで妥協するのかの判断は大事だと思います。たとえば生成AIで良質な文章を作る場合、一度のやり取りだけでなく何度もフィードバックを繰り返して、修正を続けて完成させる必要があります。むしろ、生成AIに一発でクオリティの高い文章を書かせることの方が難易度は高いと思います。
「生成AIを使えばもっとラクに仕事ができる」という発想を持つ
竹内:読みやすい文章にするために、人間が何度も修正するのと似ていますね。
柳井氏:多くの人が良い文章か悪い文章かを判断する基準を持っていません。だからこそ、売れる言葉を導き出すために、何度も壁打ちをする必要があります。そういう意味で言えば、人間の売れるために妥協しない「執着」という気持ちが、生成AIの活用には非常に重要だと思っています。
竹内:成功している経営者は、「売れるためなら何でもやってやる」という執着心が強いですからね。執着心が強い人は売れる言葉を導き出すために徹底して生成AIを使い倒すし、「このへんでいいだろう」とすぐに妥協してしまう人は、生成AIを使っても売れる言葉にまでたどり着けない可能性がありそうですね。
柳井氏:そこが生成AIを盲信し過ぎてしまう人の懸念するべきポイントだと思っています。安易に生成AIの吐き出した答えを信じてしまうと、今度は自分で物事を考えることをやめるようになって、最終的に仕事の現場から排除されてしまいます。
竹内:生成AIの回答をそのまま使うような人材であれば、生成AIで仕事はこと足りてしまいますからね。
柳井氏:肝心なことは「生成AIを使えばもっとラクに仕事ができる」という発想を持つことです。優秀なエンジニアが最も怠惰であるように、自分がやっていることをいかに機械にやらせるかを考える努力は、今後はますます重要になっていくと思います。
竹内:話を伺っていると、生成AIの活用はプロンプトがカギを握っているような気がします。プロンプト構築のスキルアップ方法はあるのでしょうか?
柳井氏: 基本的なプロンプトのテクニックは各生成AIの公式サイトで公開されています。「ChatGPT」なら「ChatGPT」の資料、「Claude」なら「Claude」のプロンプトのテクニックが存在しており、共通しているところも多いので、まずはそこを押さえることが重要です。
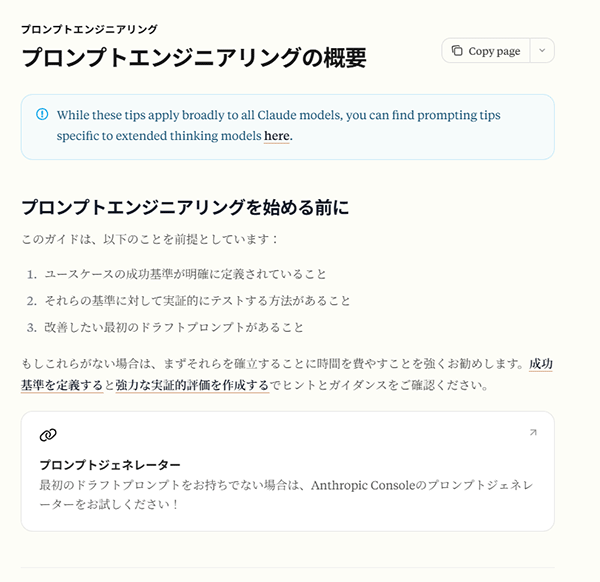
筆者出版情報
楽天市場 最強攻略ガイド ~売れるネットショップの新常識、ECの達人が教えます~
竹内謙礼 /清水将平 著
技術評論社 刊
価格 2,400円+税
「楽天市場に出店したいけど、売れるかどうか不安だ」「楽天市場にお店を出したけど、思うように売れない」「何年も楽天市場に出店しているけど、売上が少しずつ落ちている」といった悩み・課題を解消するプロの知識・ノウハウを解説。EC運営初心者、ベテラン運営者も新たな発見につながる一冊となっている。



























