Googleの「AI モード」が登場! EC事業者が知っておくべき“AI時代”のSEOの本質とその対策
ネットショップ担当者が読んでおくべき2025年8月24日~9月19日のニュース
2025年9月24日 8:00
Googleは9月9日、新しい検索「AI モード」の提供を日本語でも開始しました。スタートから約2週間。Web上には「AIO(AI最適化)」「AEO(AIエージェント最適化)」「LLMO(大規模言語モデル最適化)」といったワードが増え、早くも「AI モデル対策」をうたったSEO対策の営業も出てきたと聞きます。「AI モード」を試された方はご存じの通り、「AI モード」の結果には「AIの回答には間違いが含まれている場合があります」と注意書きが添えられています。まだまだ発展途上の「AI モード」を含めたSEO対策はどうすればいいのか。進むべき道を考察します。
ECの読者さんが進むべき“SEO”対策
Google 検索における「AI モード」を日本語で提供開始 |Google Japan Blog
https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/ai-mode-search/
要チェック記事
SEO関連
AI検索 vs Google検索 20代がAIより従来型を使う理由 | Forbes JAPAN
https://forbesjapan.com/articles/detail/81697
“調査で最も興味深いのは、利用場面による明確な使い分けが既に確立されていることだ”
“AI検索を「特に利用しない」層が50%と半数を占めており、検索利用はまだ途上段階”
“20代が目的に応じて最適なツールを見極める判断を行っている様子がうかがえる”
記事のアンケート母数は少ないですが、的を射ていると思います。
何年か前に「Z世代は検索エンジンを使わない」などと言われた頃、就活生向けのSNS講座を担当したことがあります。その際に「検索を使わないのではなく、検索以外も使う。用途によって使い分けているだけ」という言葉を聞いたことがありました。
たとえば、友達と行くお店は「TikTok」で検索し、「Instagram」でメニューなどの写真を見る、Googleマップの口コミを参考にして予約は食べログで――。就活に必要な情報はGoogleで、求人サイトの情報や経験者のブログを読むといった行動はまさに使い分けだなと感じました。
前回の記事で書いた通り、SEOのEを検索エンジンのEではなく、あらゆる場所「Everywhere」と捉えていく必要がありそうですね。
メディアがGoogleを提訴。「AI OverviewsのせいでWeb閲覧が激減」 | GIZMODE
https://www.gizmodo.jp/2025/09/google-ai-overviews-causes-a-decline-in-web-browsing.html
訴訟を起こしたのは、「Rolling Stone」や「The Hollywood Reporter」を傘下に持つ米国のメディア企業のPenske Media社です。メディアの訴えは確かに切実です。
“彼らの訴えはシンプルで、検索結果トップにAIによる記事要約が表示されると、ユーザーは記事本体を読む必要がなくなったため、トラフィックが減った”
“「Daily Mail」を運営するDMG Mediaは、AI Overviewsの提供開始以来、クリック率が89%も落ちた”
確かにアクセスの9割減は死活問題どころではない打撃ですが、AIOの影響と共に低品質なコンテンツがないか見直すなど、サイトの運営方針を刷新することも必要ではないでしょうか。しかし、Googleは一貫して下記の通り主張しています。
“AI Overviewsでは、ユーザーは検索をより便利だと感じ、より多く使うようになるので、それはコンテンツが発見される新たな機会となります。こうした根拠のない主張に対しては反論していきます”
私の周囲でも、「AI Overviews(AIO)」の登場で、確かに前年比で2~3割のアクセスが減少が認められるサイトは多く見聞きします。それでもコンバージョンが落ちているかと言われれば、そこまででもないというのが現状です。やはり質の高いコンテンツを提供し、ユーザーの興味関心を引くことに注力することも大切でしょう。
【順位計測ツールに影響あり】Googleが検索結果の表示件数の指定機能を停止 | ナイルのSEO相談室
https://www.seohacks.net/column/29216/
“Google検索では、検索結果のURLの末尾に「&num=100」という文字を付けると、検索結果を1ページに100件分のページリンクを表示させることができました”
“多くの順位チェックツールはこの仕組みを利用して、11位以降の順位もまとめて取得していたのです”
“ところが2025年9月11日頃から、この指定が効かなくなるケースが確認され始めています”
検索結果のURLに「&num=100」を追加することで、通常ユーザーが目にすることがないような検索結果の10ページ目、91~100位までをツールが表示させていたため、「Search Console」の表示回数が多く出されていたということですね。
私のクライアントでも、同様の状況は確認されており、この指定ができなくなった2025年9月11日前後の期間を比較すると5%~10%程度の減少がありました。
ランキングチェックツールを使っている方には影響が多少あると思われます。しかし、そもそも人が検索していない検索データであれば不要と思えるのですが、順位チェックは有用な側面があるので悩ましいところです。
いくつかのツールでは、すでに暫定的な対策を講じているようですので、お使いのツールのアナウンスや続報をチェックしてみてください。
それでも「AI モード」、AIO、生成AIなどの流入経路は多種多様になってきていますから、自社とお客さんのより相性の良い場所を見つけていく努力が必要ですね。
マーケティング関連
「こんな過疎町に……?」住民9割反対から“道の駅日本一”に なめことロイズが起こした逆転劇:地域経済の底力 | ITmedia ビジネスオンライン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2509/05/news023.html
じゃらんの2024年「全国道の駅グランプリ」1位に輝いた宮城県大崎市の「あ・ら・伊達な道の駅」は開業から25年間、ほぼ右肩上がりの成長を続け、年間320万人の来場、年間売上20億円を誇る大人気の道の駅。
当初は北西7kmほど先にある鳴子温泉へ向かう途中のトイレ休憩場として活用され、その後、人気に火をつけたのが表題にある「なめこ」と北海道の有名チョコレートブランド「ロイズ」。最初の火付け役のなめこ生産者は、あと1年、道の駅の開業が遅れていれば廃業していたそうです。
“もうやめようかと思っていた時に、ダメ元でここに出品してみた”
まずは人を呼ぶこと、ECサイトでいえばアクセス獲得ですね。その次にそこに来る理由となる看板商品という大切なことが実践されています。
そして、発信をすることで不思議なめぐり合わせのようなことが起こる。これはSNSでの発信で出会う可能性が生まれることと似ていると感じました。
宝くじは買わないと当たる権利さえないのど同様に、やってみたからこそわかること、生まれるものはありますよね。
ところで、なぜ北海道のチョコが宮城で? ということも本記事をご覧ください。
何がどうつながるかわからないからこそ今から動いてみる、反対意見に流されないことの大切さを学ぶ記事でした。
店員がいない「無人書店」続々、人の目気にせずじっくり吟味…コスト削減しながら「24時間営業」も | 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/20250913-OYT1T50005/
日販によると、2016年~2021年で全国の駅、駅前立地の書店の出店数は約60店舗に対し、退店数は約120店舗だそうです。倍速で減り続ける書店の新しい可能性を示唆する無人書店の取り組みを興味深く読みました。
“行きたい時に行くことができて、好きな世界に浸れる。スマートフォン的な使い方ができる点が受けているのではないか。魅力的な本を集め、来店客の期待に応えたい”
とは、店主の言葉ですが、行きたいときにスマホやPCで好きな世界に浸れるということもECサイトに通じることかと感じました。
24時間いつでも利用できるECサイトのなかでも、巨大モールが持つ、欲しい商品を翌日配送してくれるスピードや価格面に対し、中小ECが立ち向かうことは至難の業。
お店とお客さんが好きなものや世界観を共有できる場所になれることこそが、個人や中小企業のECのあるべき姿ではないでしょうか。消費者行動論の専門家、慶応大学の白井美由里教授は、
“ただしセルフサービスは人によって好き嫌いがある。安心感や快適性などのサービス向上が今後の普及の鍵になるかもしれない”
と、結んでおり、自社にとってちょうどいい距離感や温度感をサイト上に育んでいくことが今後のECサイトには重要なポイントだと個人的には考えています。
オリオンビール、Tシャツで若者浸透 グッズ販売2年で3倍の30億円 | 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC04CZU0U5A900C2000000/
2025年9月25日に東京証券取引所への上場を予定しているオリオンビールのグッズ販売が3倍に成長しているという記事です。同社のアパレルグッズを購入した若者たちは、
“かわいいし、沖縄に行ったことがすぐにわかる。たくさん写真を撮りたい”
“ビール会社とは意識していない”
と話し、アパレル分野で認知が高まっている様子がうかがえます。
私が若い頃に流行したアパレルのロゴを調べてみると、海外のオイルメーカー、アーティストのアルバムジャケットだったりということがありました。ユニクロと企業のコラボTシャツでも、広く企業の商品ロゴなどが売り出されていますが、歩く広告塔たちによって「見たたことがある」と認知度が上がることはプラスですね。
小さなお店でも看板やロゴのグッズをオンデマンドで制作しているところもあります。当社も会社のロゴを入れたアパレルグッズがあります。「無名の企業のグッズを誰が買うねん」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現に有名な芸能事務所の社長が愛用しています。
自社を愛することを1人であろうと、こうしたグッズを身に着け、始めることは将来、オリオンビールのようなブランディングにつながるかもしれませんよね。
そうして私は今日も自社のロゴ入りパーカーとサコッシュを身につけ外に繰り出します。
今、みなさんにお伝えしたいこと
“なにかを成し遂げたいのなら、死ぬ気で働かないといけない時期が必ずあると思うんだ” | 岩井圭也 サバイブ!特設サイト(祥伝社)
https://www.shodensha.co.jp/survive/
これはベンチャー企業舞台にした小説「サバイブ!」からの一節。
就活中に難病に倒れ、退院を機に起業した主人公と仲間たちのお話。動画制作会社としてスタートしたものの決まったのは社名だけという、いかにも青春なテーマなのですが、実在するベンチャー企業をモデルに書き起こされた作品です。
流行語にもなった「倍返し」のような爽快復讐劇でもない本作は、創業から20年後に生き残っているベンチャー企業は0.3%という厳しい現実と夢とを垣間見させてくれる物語です。
2020年1月に創業した株式会社ユウキノインも9月で7期目を迎えました。中小企業庁のデータによればベンチャー企業の生存率は、5年後で約15%で10年後で6.3%と言われています。
7年であれば、その間の11%ほどでしょうか。当社も現時点でなんとか1/10に生き残ることができました。
この「ネッ担まとめ」を一緒に担当する石田さんは2011年に起業(すごい!)。中林さんは先日、法人を設立されました(おめでとうございます!)。
いつも読んでくださる読者の皆さんとも一緒に15年、20年と生存できるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
それではまた次回! 酒匂(さこっち)の「ネッ担ニュースまとめ」をよろしくお願います。
「新・ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」は以下の専門家が連載しています。
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。


















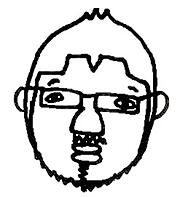

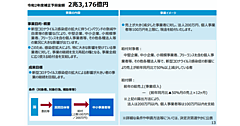
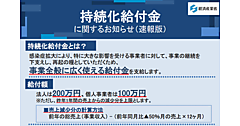

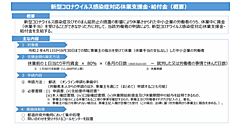
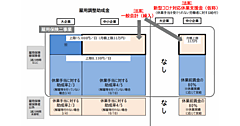



AIとSEOを取り巻く情報を収集・分析すると、SEOの基本原則は変わらず、「ユーザーのニーズに直接応えられるような、高品質で役に立つオリジナリティのあるコンテンツを、信頼できる人やお店が作成していくこと」に行き着きます。
生成AIが劇的に進化し、ECを含めた業務の改善や効率化につながった事例は増えています。検索での変化はどうでしょうか? 人々の調べ方、探し方の原則はそのまま、媒介するツールの置き換わりによって、ゆるやかに進化、変化していくような気がしています。
つまりはE-E-A-T(Googleがサイトやコンテンツを評価するための基準)、「専門性(Expertise)」「経験(Experience)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼(Trustworthiness)」が重要で、Googleの掲げる概念は至極、当然のことだと再認識しているところです。
「何を言うか」よりも「誰が何を言うか」をGoogleが重要視していることを踏まえると、自分が何者かになるしかないと考えられます。
“小さいお店だから”“無名のブランドだから”といって歩を止めるのではなく、愚直に自分たちが「どこで何をしていて、それをどんな人たちへ届けようとしているのか、何を知っていて、何を解決できるのか」を丁寧に発信していくことが、真のSEO対策ではないかと思うのです。
私が「さこっち」というニックネームをハンドルネームとして使用するSNSのアカウントの数を調べたところ、部分一致も含め約250ほど確認できました。
「AI モード」で「さこっちとは誰のこと?」「さこっちって?」と聞いてみると、最上位に「代表的な人物としては、SEOコンサルタントの『酒匂雄二』さんがあげられます」のように生成されることが多いです。
私のXのアカウントは、敢えて本名を掲載していません。しかし、Googleは自社サイトのニックネームや会社名などとひも付けるため、オーガニック検索でも、会社のサイト、Xの私のアカウントが並んで表示され、その後には私ではない同名のInstagramのアカウントが並びます。
起業当初「さこっちと名乗っているのに、さこっちで全然上位に出てこない。SEOをしているならさこっちで1位になれ」と言われたことがあります。確かにSEOを生業としている者として、せめて「さこっち」で1位にならねば!と、試行錯誤しました。
14年間在職した前職時代からECやSEO関連の登壇の機会がありましたが、起業して5年の今、酒匂雄二の上位表示は現職のものばかり。前職時代の情報は20位あたりでようやく出てくるようになりました。
この結果から、現在進行系の関連度、情報の鮮度などが評価されていることが考えられます。みなさんの“Now”を発信していくことが、お客さまに見つけてもらう“SEOのいろは”の“い”なのではないでしょうか。
この記事を読んでくださる多くの方がEC関連のお仕事をされていることでしょう。皆さんは、どんな顧客向けに、どんな商品やサービスを、その知識を提供できる何者なのか――ということを発信していますか?
これが、皆さんが進むべき“SEO”対策なのかもしれないですね。