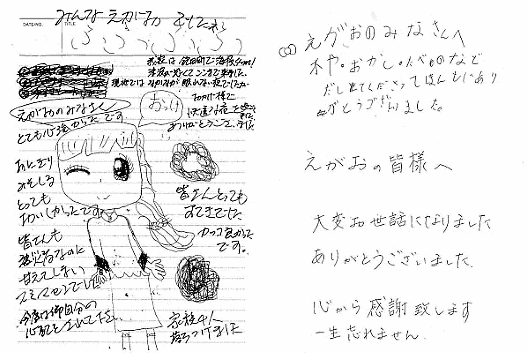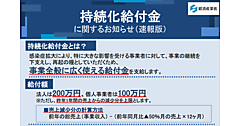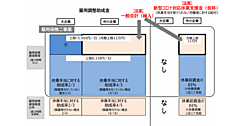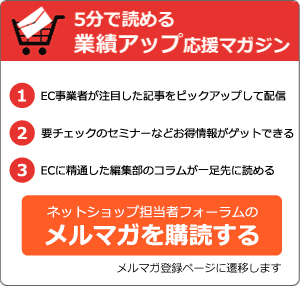熊本市に拠点を構える健康食品の通販・EC会社えがおは、熊本地震の被害を受けた1社。本社の一部損壊、事業の一部ストップなど企業活動に影響が発生した一方、周辺地域への支援に奔走する。こうした未曾有の事態が起きると、企業には経済活動だけではなく、支援活動など大きな役割が求められる。未曾有の事態に企業はどう動くべきか。BCP(事業継続計画)や地域支援といった観点から、えがおの震災後を追う。
早期再開のカギは一極集中避けたリスク分散体制
4月14日、震度7の地震に襲われた熊本県。熊本市に本社を構える、えがおの経済活動にも直撃した。震源地付近ではあったが、「耐震構造をしっかりとした設計にしていた」(えがお広報担当者)ということもあり、被害は窓ガラスや壁の破損などにとどまった。
スタッフの安否は確認できたが、自宅の損壊など被災したスタッフは少なくない。いまでも避難所など自宅以外から出社している従業員もいる。
大きな地震が発生した後の4月16日、商品受注の大きな役割を担うコールセンターの運営を中断したが、17日午後には一部再開。物流インフラの寸断といった影響を受け配送面が一時ストップしたものの、4月22日前後には配送を再開した。ただ、物流インフラの寸断などの影響は現在も続き、荷物の配送に遅れが生じている。
えがおの通販ビジネスは、コールセンターでの顧客応対が中心。つまり、コールセンターの寸断は企業業績に直結する。また、本社でスタッフが稼働できなければ事業を継続していくことは難しい。えがおはどうしたのか?
まず熊本市に構える社屋。2014年に完成した新社屋は耐震化に優れた構造で設計。電源装置や貯水タンクを設備として備え、未曾有のトラブルにも対処できるようにしていた。その結果、停電や断水といった影響を避けることができた。
また、物流拠点は全国地域に複数分散。コールセンターの一部はアウトソーシングしていた。一極集中による効率化を求める体制ではなく、リスク分散を重視したビジネス設計を施していたことが、コールセンターや商品配送の早期稼働の実現につながった。
えがおの広報担当者もこう説明している。
物流拠点を複数個所に分散させていたり、コールセンターの一部をアウトソーシングするなど、一極集中していなかった点が早期復旧を可能にしたと考えます。
ちなみに、コールセンターを4月16~17日の間、一時ストップしたのは、地震による影響と社屋に避難した周辺住民など約300人の避難者対応を行うため(詳細は後述)。駆けつけることができた従業員が総出で、避難者の対応にあたった。

周辺住民への支援に奔走、避難所として本社を開放
4月14日の地震発生直後。えがおは本社1階のレセプションホールを近隣住民の緊急避難所として開放した。不安になった地域住民がえがおの社屋に避難してきたため、急遽、緊急避難所として臨時開放。4月17日の昼頃まで避難所として提供した。
14日以降、本社に駆け付けることができた従業員は総出で避難者に対応。ただ、公設の避難所ではないため、当初、支援物資は皆無だった。スタッフが確保した水や食料品をまずは提供。自宅からお米や炊飯器を持ち出し、おにぎりやおみそ汁も作ったという。

14日夜は約30人、15日は10人ほどが宿泊し、社員数人が対応。16日未明の本震後は、地域住民が続々と避難するためにえがおの本社を訪れ、最も多いときで約200人、総勢300人ほどが滞在した。
その後、スタッフたちは各避難所を回り始める。4月19日からは野菜不足解消のために主力の青汁を提供。スポンサーを務めるサッカーJ2の「ロアッソ熊本」の選手とともに、子どもたちを対象としたサッカー教室を開くなど、支援活動を継続している。

その一方、北野忠男社長は被害の大きかった益城町や西原村、熊本市内の被災地域や避難所に足を運んだ。その中で、家屋の倒壊・損壊などで自宅へ戻れない人たちの切実な声を聞いた。


えがおは「次の住まいが決まるまで長期的にできる支援がないか」と模索。急遽、熊本市と連携して熊本市東区東本町にある旧本社ビルを避難所として開放した。4月27日現在、約60人の周辺住民などが避難生活を送っている。

えがおは、経営理念の下、ボランティア活動や社会貢献事業を積極的に行っている。震災後、自らも被災の影響を受けながらも、周辺地域への支援活動に精を出すのは徹底した経営理念が日頃から実践されているからだろう。
こうした状況や取り組みを踏まえ、えがおの広報担当者は次のようなメッセージを寄せてくれた。
全国の皆さまからの温かい励ましのお言葉やご支援、心より感謝申し上げます。復興までは長い道のりになると思いますが、地域の方とともに1日も早い復興のため、全社一丸となって取り組んでまいります。