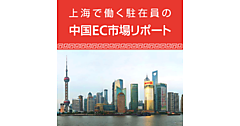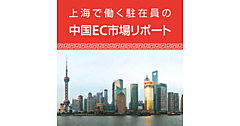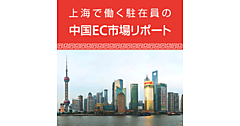越境ECは小売で行うべき? 卸で展開すべき? 海外展開に悩む問題の正解とは。
中国に駐在し、実際にECも手がけるエフカフェの高岡正人取締役が中国ECの状況をレポート(vol.14)
2016年3月7日 11:30
越境ECを始めるにあたり、自社で直接現地の消費者に売るのか、卸経由で販売するのかは悩みどころ。今回は両方のメリット・デメリットを考察していきます。前回連載で2015年12月に中国で開かれた「第2回 World internet conference(世界インターネット大会)」で、京東商城(JD、中国モールシェア2位)とアリババ(モールシェア1位)のスタンスの違いを紹介しました。スタンスの違いから、日本企業が越境ECを行う際のファーストステップをお伝えします。
アリババとJDの両トップで異なるECへの考え方
2016年2月19日から21日まで開催された 「2016亜布力中国企業家フォーラム第16回年会」で、JDの劉強東(リウ・チアンドン)CEOはECの事業収益に関して、次のように発言しました。
事業ドメインがメーカーの場合、自社でネット通販を行うことをやめ、卸や代理店などに任せて自社のEC事業部をリストラすべきだ。
この背景として、ある著名な靴メーカーを例にあげた。総売上約66億元(約1200億円)のこの会社は、ネット通販売り上げは3分の1である22億元(約440億円)だったが、利益はわずか1000万元(約2億円)であることを指摘。仮に代理店へのアウトソーシングを想定した場合、利益は3.8億元(約76億円)になるだろうと試算しました。
私が推測するところ、JDは自社で卸販売も行っているため、そこへの誘導を意図した発言だと思いますが、このコメントは物議を醸しています。
一方、アリババ会長のジャックマー氏は、次のように指摘します。
企業は自分たちの店舗を通じ、お客さまのニーズや心の声を聞くべきだ。
商品を提供することが一番大切なので、もっと積極的に自社でECを行うべきだと発言しています。

この両者の発言を聞いて思ったことは、日本企業が越境ECを考える際のファーストステップと酷似しているということです。
越境ECにおける卸と小売のメリット、デメリット
中国展開を考えているさまざまな企業の担当者などとミーティングをしていますが、まず相談されることは「卸で商品を展開すべきか」「小売で展開すべきか」ということです。
(当たり前ですが)企業によって、全く異なります。
越境ECの観点で簡単に比較します。
卸のケース
メリット
- 買い取ってもらえるので在庫リスクがない
- 個配モデルではないので一括納品で手間がかからない
- ロットではける
- ゼロからブランディングを担ってくれることもある
デメリット
- 顧客接点がない
- 1商品あたりの利益が少ない
- 商品改善などがしにくい
- ある程度有名でないと卸ルートに乗らない
小売のケース
メリット
- 直接顧客にぶつけるのでニーズなどをマーケティングできる
- 顧客リストを保持できる(ただしモールだと制限)
- 販売価格をコントロールできる(メーカーなどはなお可能)
デメリット
- 大量に売れない可能性もあり、在庫リスクがある
- 個配モデルを構築する必要がある
最大のキーは顧客とどのようにつながるのか
越境ECの場合、最大のキーになるのは、顧客とどのようにつながるのかです。
もちろん日本人ではなく中国人なので、消費行動は異なります。だからこそ、顧客と直接的につながることは価値が高く、中長期的にいろいろな施策が実現可能となります。
日本国内のように、卸の手を借りないと流通しにくい状況とは異なり、まだまだ発展途上段階とも言える中国において、ネットでの日本商品販売は多くのチャンスが存在します。3年前に本格的な越境ECのスキームができ、多くの企業が同じスタートラインに立てる機会はビジネス的にそうあるものではありません。
ただ、あくまで現状はモール内での顧客接点になるので、そこは制約条件があることを忘れてはいけません。
一方、商品を認知してもらうのはそれなりの時間とコストがかかってくるため、メーカーであれば卸からスタートし、その後小売も行っていくありだと思います。
2015年中盤あたりからお陰さまで問い合わせが殺到しています。今年は間違いなく多くの企業がスタートラインに立つ年になると感じています。