Googleが発表した新たなAIエージェントの決済規格「Agent Payments Protocol(AP2)」は、すでにSalesforce、Shopify、Etsyなどが導入しています。透明性が高く、安心安全な取引につながることから、企業の信頼性、説明責任、セキュリティといったAI活用で課題になりやすい項目の解決にもつながるとGoogleは説明しています。
60社超が導入し始めている「Agent Payments Protocol」とは?
Googleは、ユーザーの代わりに自律的に動くソフトウェア「AIエージェント」がユーザーに代わってオンライン決済を処理できる近未来を見据えています。その新たなプロトコル(通信ルールや手順)である「Agent Payments Protocol」は、すでに60社以上の企業が導入しています。
Googleは9月16日に配信したリリースで発表した「Agent Payments Protocol」は、AIエージェントが消費者の直接的な操作を必要とせず、安全にオンライン取引を完了できるようにする標準規格です。
「AP2」の概要・有用性(動画はGoogleのニュースリリースから追加)
Googleは「AP2」について、「ユーザー、販売者、決済プロバイダーがあらゆる種類の決済方法を使って安心して取引できる、決済に依存しない枠組み」を確立するものだと説明しています。
発表時点で、初期の支持企業としてMastercard、PayPal、American Express、Coinbaseといった決済会社、さらにSalesforce、Shopify、Cloudflare、Etsyなどのテクノロジー企業が名を連ねています。
American Expressのデジタルラボ担当副社長ルーク・ゲブ氏はリリースでこのようにコメントしています。
AI主導のビジネスが拡大するなかで、それを提供する企業の信頼と、エンドユーザーへの説明責任はこれまで以上に重要です。「AP2」は顧客を保護し、次世代のデジタル決済を可能にするためのプロトコルであり、American Expressはその創出に貢献できることを嬉しく思います。
AIエージェントが担う役割、EC活用の状況と課題
ユーザーに代わり自律的に動く特性を持っているAIエージェントは、予約の調整、サブスクリプションの管理など、すでに幅広いタスクをこなしています。
GoogleがAIを活用した購買体験の向上を強化しているように、ECの分野でも、商品検索、比較、さらには決済の自動化までをAIでサポートする事例が増えています。
「エージェントコマース」と呼ばれるこの新しい技術は、大規模言語モデルを搭載したエージェントがユーザーの意図を解釈し、行動に移すことを中心としています。
しかしながら、エージェントコマースが利便性を高める一方で、AI活用にあたってユーザーの承諾がきちんと得られているか、取引の正当性が保たれているか、企業の説明責任を果たせているか――といった課題も浮かんでいます。
従来の決済システムは、人が購入を承認することを前提に設計されています。しかし、昨今はAIエージェントがショッピングの一部を担うようになり、Googleは「安全で検証可能な取引を実現するために、業界全体で共有できる手引きが必要だ」と説明しています。
Googleが「AP2」に期待する信頼構築+ルール構築
そこで登場したのが「AP2」です。Googleは「『AP2』はAI主導の新しいビジネスを支える信頼の基盤を提供する」と言います。
さらにGoogleは「『AP2』が「AIエージェントと販売者の間で安全な取引を行うための共通言語」を確立し、エコシステムの断片化を防ぐ」と説明。このプロトコルは、クレジットカード、ステーブルコイン(仮想通貨の一種)、リアルタイムの銀行振込など複数の決済方法をサポートし、スケール可能な一貫した体験を提供するそうです。Googleは「AP2」が、金融機関にとっても、リスク管理を行う上で必要な明確なルールを構築する仕組みだとしています。
「AP2」 の仕組み
消費者行動に伴う「カートのマンデート」「意図のマンデート」
「AP2」の中心には「マンデート(委任状)」と呼ばれる、改ざん不可能な暗号署名付きのデジタル契約があります。
これらは暗号技術で署名され、改ざんが極めて難しい記録で、ユーザーが取引を許可したことを証明するものです。
各マンデートは、検証可能な証明書を伴っており、それを基にユーザーの行動やデータをトラッキングできるようになっています。
たとえば、ユーザーが「白のランニングシューズを探してほしい」とAIエージェントに頼むと、それは「意図のマンデート」として記録。その後、AIエージェントがショッピングカートを提示し、ユーザーが価格とアイテムを確認して購入を承認すると、「カートのマンデート」が発行され、価格や内容が確定されます。
企業が果たすべき説明責任をサポート
ユーザーが不在でもAIエージェントが条件(価格上限や日時など)を満たした際に、自動で購入するよう指示することも可能です。
たとえば、ユーザーが自分のエージェントに「100ドル以下でコンサートチケットを買って」と指示。その際、「意図のマンデート」が、価格上限やタイミングといった条件を定めます。その条件が満たされると、AIエージェントは自動的に「カートのマンデート」を生成し、購入を完了します。
いずれの場合も、一連のマンデートのつながりが、ユーザーの意図と決済実行を結びつけます。Googleは次のように説明しています。
この一連の流れ――ユーザーの「意図」から「カート」へ、そして支払いまで――は、後から取り消しできない記録として残ります。これによって「誰が承認したのか」「取引は本物か」といった重要な疑問に答えることができ、企業が果たすべき説明責任のための明確な基盤が築かれます。
「AP2」の活用例
Googleは、「AP2」がどのようにECのビジネスモデルを変革する可能性があるのか、いくつかの事例を紹介しました。
条件に合う商品を自動で購入
たとえば、緑色の冬用ジャケットを探しているユーザーが「その色なら20%まで高くても購入して良い」と同意するケースです。AIエージェントは在庫状況を常にチェックし、ユーザーの条件に合う商品を見つけるとすぐに購入を完了します。
ユーザーのスケジュールに合わせた割引を提案
別の例では、特定の店舗で自転車を探しているユーザーが、自分の旅行日程をAIエージェントと共有します。AIエージェントが、その情報を店舗側のAIエージェントに共有すると、店舗のAIエージェントはユーザーの旅行日程に併せて、自転車、ヘルメット、荷台などを対象とした時間限定の割引を提案します。
横断的な組み合わせに対応
さらに複雑なワークフローも可能です。たとえば、週末旅行を計画しているユーザーが「航空券とホテルを合わせて700ドル以内で予約して」とAIエージェントに指示します。するとAIエージェントは航空会社やホテルのシステムを横断的に調整し、条件に合う組み合わせを見つけて、両方の予約を一度に完了します。
仮想通貨への対応と企業の利用
「AP2」はクレジットカードだけでなく、ステーブルコインや暗号通貨など幅広い決済方法に対応します。
GoogleはWeb3エコシステムでの利用を広げるため、仮想通貨や暗号資産の取引をサポートするCoinbase(コインベース)、MetaMask(メタマスク)、Ethereum(イーサリアム)、 Foundation(ファンデーション)などと共同で「A2A x402」という拡張プロトコルを立ち上げました。これはAIエージェント主導で暗号通貨決済を安全に行うための仕組みです。
また、複数のパートナーが「AP2」対応のAIエージェントを構築中で、Googleの「AI Agent Marketplace」に登場予定です。開発者はGitHub(ギットハブ)の公開リポジトリを通じてプロトコルにアクセスでき、その発展に貢献できます。
企業ユーザー向けには、クラウドサービスの調達やソフトウェアライセンスの調整を、リアルタイム使用状況に応じて自動化するなどの利用が想定されています。
Googleのエージェントコマース推進戦略+AIエージェント活用事例
「AP2」はGoogleが推進するエージェントコマース戦略の一部です。
米国のEC専門誌『Digital Commerce 360』が5月に報じたところによると、Googleは「エージェントチェックアウト」と呼ばれる新機能を開発中です。これは、ユーザーが設定した条件に基づいて、買い物の一部を自動化できる仕組みです。
この分野には、他の企業も次々と参入しています。
AIを活用した検索エンジン「Perplexity(パープレキシティ)」は、Google Chromeに対抗する新しいAIブラウザ「Comet(コメット)」を展開。このブラウザには、商品を検索・比較し、購入まで行えるエージェント機能が備わっています。
2025年初めには、Firmlyが提供する、AI商品検索やチェックアウト機能などのソリューション「Firmly.ai」のチェックアウト技術を統合し、さらにPayPalと提携して、検索中に直接決済できる仕組みも導入しました。
ロイターの報道によると、OpenAIも同様のエージェント機能を持つブラウザを開発中です。「ChatGPT」を開発したOpenAIは、eBayやEtsyと協力して「Operator(オペレーター)」というエージェントコマースツールのテストも行いました。一方、Amazonは独自のAIエージェント型ショッピング機能「Buy for Me」を導入しています。
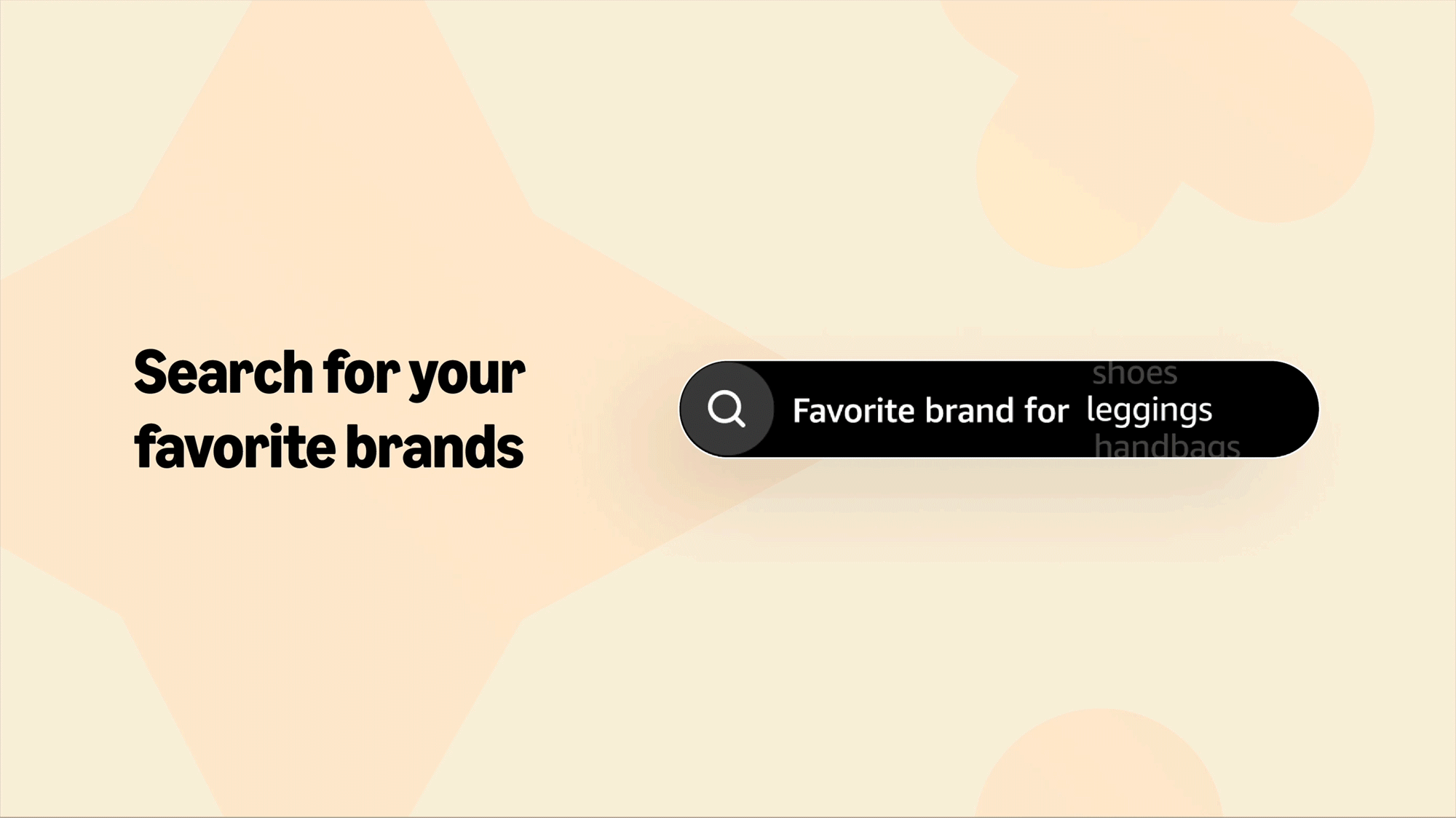
この分野はまだ発展途上ですが、こうした多くの取り組みは最終的にAP2や類似の標準規格をサポートする可能性があります。業界全体が、AIエージェント主導の買い物を支える「安全でスケール可能な枠組み」の実現に向けて動いているのです。



























